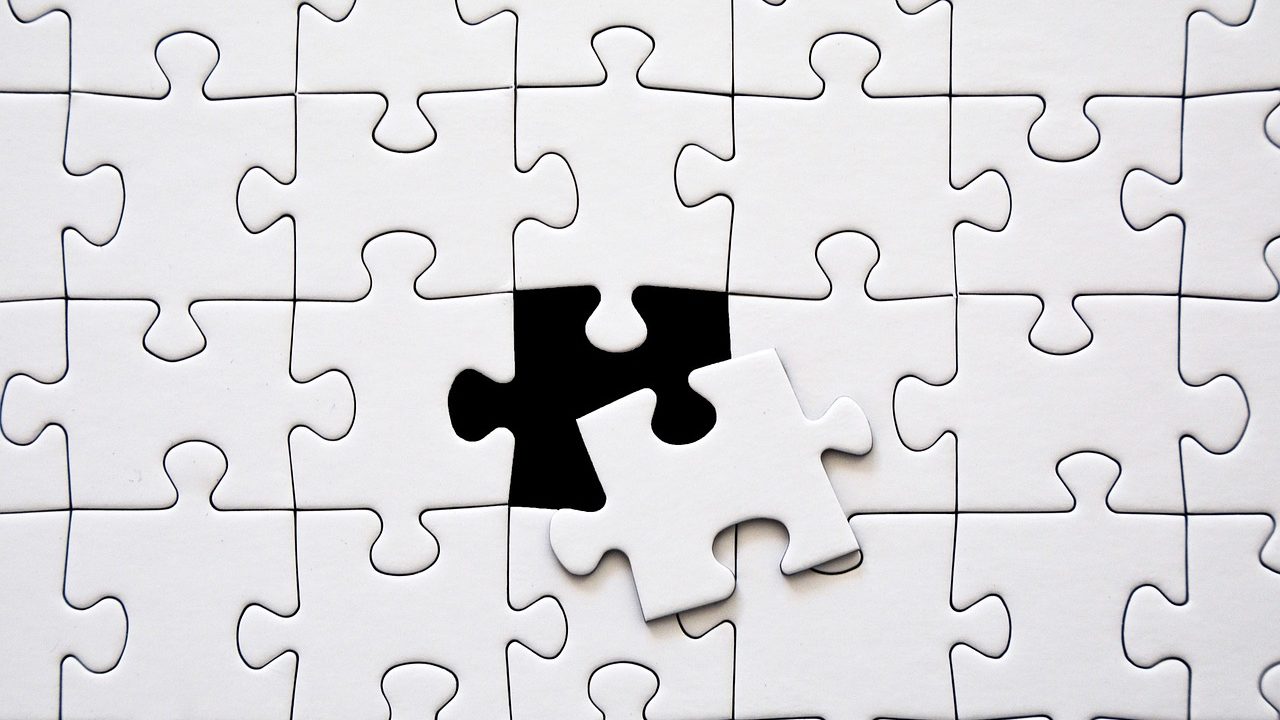特許翻訳の実務では、スタイルガイドに基づいて作業を行うのが一般的です。しかし、スタイルガイドが提供されていても、対応に悩む場面も多くあります。
中でも悩ましいのが、同義語の訳し分けをどこまで厳密に行うべきか、という判断です。
特許明細書の和訳では、原則として、同義語であっても原語が異なれば異なる訳語を使用することが求められます。ただこのルールを厳密に適用すると、最適な訳語が使用できず、やや不自然な訳文になってしまうこともあります。
私はこれまで、厳密な訳し分けが求められている場合は極力訳し分けを行ってきました。しかし今では、「訳し分けをした結果、原文と意味がずれていないか」ということを強く意識するようになっています。
それは、過度な(不自然な)訳し分けに起因して特許出願の審査において明確性違反であると指摘される可能性がある、と考えられる事例を目にしたことがきっかけです。
以下がその事例です。
(2)
・請求項 1
請求項1には「培養しかつ増大させ」と記載されているが、培養した細胞の「増大」は一般的な表現でなく、「増殖」と同義なのか、(増殖ではなく)細胞の大きさを「増大」させることなのか、あるいは別の技術的意味があるのか、不明確である。
したがって、請求項1に係る発明は明確でない。
上記は、特願2022-133783(特開2022-169705)の経過情報から確認できる「拒絶理由通知書」からの引用です。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-169705/11/jaから公開番号をクリックし、「特開2022-169705」右側にある「経過情報」→「経過記録」→「拒絶理由通知書」をクリックすると見られます。
この出願は分割出願(子出願)で、その親出願はPCT出願され、国内移行されたものです。つまり、親出願時に提出された翻訳文における訳語の選択が、この拒絶理由に大きく関係しているといえます。
そこで、請求項1の原文と訳文を引用します。青色太字部分が該当の部分です。
原文
1 ) A method for introducing genetic modifications at different loci of a primary immune cell, comprising the sequential steps of:
a) subjecting said primary immune cell to a first electroporation step to introduce at least a first sequence-specific reagent into said immune cell;
b) cultivating said primary immune cell thereby enabling said first sequence- specific reagent to modify its genome at a first locus,
c) subjecting said primary immune to at least a second electroporation step to introduce at least a second sequence-specific reagent into said cell,
d) cultivating and expanding said primary immune thereby enabling said second sequence-specific reagent to modify its genome at said second locus.
(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/WO-A-2018-007263/50/ja)より引用
訳文
【請求項1】
初代免疫細胞の異なる複数の遺伝子座において遺伝子改変を導入するための方法であって、
(a)該初代免疫細胞を第1のエレクトロポレーション段階に供して、少なくとも第1の配列特異的試薬を該免疫細胞に導入する段階、
(b)該初代免疫細胞を培養し、それによって該第1の配列特異的試薬が第1の遺伝子座においてそのゲノムを改変できるようにする段階、
(c)該初代免疫を少なくとも第2のエレクトロポレーション段階に供して、少なくとも第2の配列特異的試薬を該細胞に導入する段階、
(d)該初代免疫を培養しかつ増大させ、それによって該第2の配列特異的試薬が該第2の遺伝子座においてそのゲノムを改変できるようにする段階
の逐次段階を含む、方法。
(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-169705/11/jaより引用)
つまり、expandingを「増大させ」と訳したところ、培養した細胞の「増大」の意味するところが不明であると明確性違反を指摘された、ということになります。
(その他、本件では「a primary immune cell」に関する用語の揺れなども同一の拒絶理由通知書に記載されていますが、ここでは省きます。)
審査官の指摘は、一翻訳者の立場からも納得できるものです。
確かに「増大」は、程度や大きさが大きくなるという意味で使用されることが多いでしょう。
そして、細胞の数を増やす操作を「増殖」と呼ぶことが一般的であるため、わざわざ増殖ではなく増大と記載されているのだから増殖とは異なる意味で使用されているのでは、と考えるのも自然であるように思います。
また私見ですが、この文脈ではさらに、「培養しかつ増大させ」と、「該第2の配列特異的試薬が該第2の遺伝子座においてそのゲノムを改変できるようにする」とが「それによって」で接続されていますが、両者の因果関係がわかりにくいようにも感じます。これも「増大」の意味を不明瞭にしているように思われます。
この文脈でのexpandingは、やはり「増殖」という意味で使用されていると考えられます。
ただ、ここからは推測になるのですが、担当された翻訳者さんも「増殖」と訳すのがベストであると考えながらも、厳密な訳し分けをクライアントから求められて「増大」と訳さざるを得なかったのではないでしょうか。
というのも、この翻訳文では以下のようにきっちり訳し分けがなされているからです。expansionはすべて、請求項と同一の文脈(細胞をexpandする)で使用されています。
expansion: 増大
proliferation: 増殖
growth: 成長(ただし、growth factorは「増殖因子」)
proliferationは「増殖」以外には訳しにくいため、これに「増殖」をあてるとすると、expansionには他の語をあてるほかなくなります。「(数を)増やす」なども使用可能な箇所は限定的ですし、苦肉の策としてカタカナ語にするのもこの例では無理があります。
そのため、これら3つの用語の厳密な訳し分けを求められた場合、明細書全体を見て受け入れがたい違和感がなければ、私も上記のように訳し分けすることが多いです。ですので、この事例は私にとって他人事ではありません。
翻訳者が「増大よりも増殖が訳語として適切」と理解しながらも指示を尊重して厳密に訳し分けを行ったら審査で問題となった、という状況(あくまで推測です)は、誰にとっても喜ばしいことではないように思います。
確かに指示には「極力」訳し分けるように、などと記載されていることが多いのですが、その「極力」の程度の解釈は人それぞれではないでしょうか。
訳し分けるのに十分な数の類義語が存在する限り訳し分けるのか、それとも今回のように明確性違反として指摘される可能性があるならば他の用語と同じ訳語を用いてでも最適な訳語とするか、の判断の統一は難しいように思います。
厳密な訳し分けを求められる場合は、私は現時点では以下のように対応しています。
- まず請求項で使用される用語に優先的に適切な訳語を使用する(明細書全体との兼ね合いもあるので、できる限り、ですが)。
- 若干不自然であっても、訳し分けが可能な限り訳し分ける。
- その結果、不自然となった箇所(特に請求項中)についてはその旨をコメントし、適切な訳語や他の訳し分けの候補を記載する。
結局のところ臨機応変に対応するしかない、という結論にはなりますが、自分が訳した明細書が無事特許査定されるように、翻訳者として手を尽くしたいと思っています。
ちなみに、今回取り上げた出願の親出願(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2018-568746/10/ja)の請求項にも今回と同様の記載がありますが、指摘もなく特許されています。
また、同じ文脈で請求項に「増大」を使用している明細書を数件確認してみましたが、その中では同じ指摘を受けた出願は見当たりませんでした。
出願書類全体を隅々まで見ていないので何とも言えませんが、文脈もさることながら、審査官次第、タイミング次第、ということかもしれませんね。
経過情報、特に拒絶理由通知書とそれに対する意見書は、翻訳者にとって参考になる情報にあふれています。
特に自身が翻訳した案件ですと、内容もわかっていますのでより興味深く経過を追うことができますし、もしかしたら今回取り上げたような状況が生じているかもしれません。
一度目を通してみるとさまざまな発見があると思います。