このページでは、未経験から専業フリーランス翻訳者になった経験をもとに、どのように学習を進めていくべきかなどについてまとめています。
Contents
未経験から翻訳者になれるのか
「未経験から翻訳者になれますか」と聞かれたら、
なれますが、楽ではないです、と答えます。
私はゼロ(翻訳未経験・理系バックグラウンドなし)から3年で、特許翻訳者(英日)として月平均売上40万円は見込めるレベルに到達しました。
「ゼロ」といってもそれまでの学習方法や環境(特に投資できる時間とお金)は人それぞれなので、どのくらいの期間がかかるかも当然ながら人それぞれです。
ただ、未経験だと相当頑張る必要があること、そして結果はすぐには出ないことを頭に入れておく必要があります。
私の翻訳者までの道のり
まず、私がどのようにゼロから翻訳者になったのかをまとめます。
後に書きますが、これが正解というわけではなく、むしろかなり遠回りしていますので、これを参考にせず、次の「翻訳者を目指すうえで大切なこと」を参考にしてください。
学習開始時の状態
属性:37歳、女性、独身
学歴:
外国語学部ではない文系学部卒、第二外国語として中国語を学び在学中に1年半語学留学
職歴:
フルタイムの会社員(残業はほぼなし)
それ以前の職歴も含めて基本的に事務(貿易関係多め)の仕事。中国での勤務歴あり(現地採用として)
語学力:
TOEIC900点台前半、英検準1級、中検1級、HSK6級
中国語は翻訳者を目指す前に学習していましたが、英語は30代からはほぼ放置状態でした
翻訳者になるためにやったこと
すべてではないですが、主なものを時系列でまとめます。
また、別のページで紹介していますが、私は「レバレッジ特許翻訳講座」を利用して、英日特許翻訳者になるための学習を開始しました。
| 学習開始から | 内容 |
| ~5か月目 | 高校レベルの化学・物理の学習(日本語の特許明細書を少しずつ読みながら) |
| 5か月目~11か月目 | 日本語の特許明細書を読む、特許明細書の翻訳学習 |
| 11か月~1年3か月目 | トライアル受験、並行して特許明細書の翻訳学習(1年3か月目でトライアル初合格) |
| 1年4か月目~1年10か月目 | 会社を退職して専業フリーランスを目指す(1年4か月目)。 医療系の産業翻訳者を目指して方向転換する。その後、とあるきっかけから中国語の医療系の産業翻訳のトライアルを受け、合格し継続的に受注する。並行して英日医薬翻訳の学習をする。4社トライアル受験し、2社合格するも、この期間には仕事の打診なし |
| 1年11か月目~2年3か月目 | 上記がうまく軌道に乗らなかった(目標売上に満たない)ため、再度方向転換。バイオ・医薬分野の特許翻訳での参入を目指して学習する。この期間に、バイオの基礎学習、特許明細書を日本語で大量に読むこと、明細書の翻訳学習を行う |
| 2年3か月目~3年目 | 特許(バイオ系)のトライアルを受け、合格し、これまで(学習開始から3年経過)継続的に受注している。この期間は仕事がメインで、学習は案件で出てきた部分をもう少し広く調べる程度 |
後でもう少し詳しく書きますが、特にやってよかったと思うことは、はじめに化学・物理を学習したこと、そして再度特許翻訳(バイオ・医薬系)に挑戦するときに日本語の特許明細書を大量に読んだことです。
逆にやるべきではなかったことは、途中で中国語の医療翻訳や英日の医薬翻訳にシフトしたことです。
当たり前ですが、リソースを分散させるとすべてが中途半端になり結果が出るまでに時間がかかります。
翻訳者になるために費やした時間
トライアルに初合格するまでにかけた時間が約3300時間、そこからさらに約4600時間が経過して(産業翻訳の学習や仕事も含みます)、バイオ系のトライアルに合格し安定稼働するようになりました。
何千時間、と言われてもピンとこないかもしれません。
1日どれくらいの時間を使っていたかというと、会社員の時は平日6時間~7時間、休日14~15時間、退職してからは平均13時間ほど(学習に専念しているとき)、11時間ほど(仕事メインのとき)の時間を投入してきました。
生活のほぼすべてです。
この時間には純粋な学習時間・仕事時間だけでない時間(学んだことのブログ記事を書く時間、トライアル対応時間など)も含まれているのであくまでも参考値です。
そして、かなり回り道をしたり、必要ないところに時間をつかっていたので(特に、途中分野を変えたり言語を変えたりしていた部分です)、私は時間を掛けすぎています。
同じようなスタート地点からでも、もっと早く到達することは可能です。
ここでお伝えしたいのは、
・ゼロから翻訳者になるにはある程度まとまった時間がかかる(少なくとも数千時間レベル)ということと、
・かといって闇雲に時間をかければよいわけではなく、正しい方向性を持って学習を進めていくことが大切である
ということです。
では、正しい方向性とは何でしょうか。
あくまで私の考えですが、以下でお伝えする3点を念頭に入れて進めていけば、貴重な時間を無駄にすることは少なくなると思っています。
翻訳者を目指すうえで大切な3つのこと
はじめにまとめますと、私は下記のことが大切であると思っています。
- 期限付きの目標を設定すること
- 翻訳対象を訳すための学習に注力すること
- 語学力だけではなく総合的な「翻訳力」を伸ばすこと
1. 期限付き目標を設定すること
「もう少し自信がついてからトライアルを受けよう」「この本を一通り学習してから次の学習に移ろう」なんて思ったことはないでしょうか。
まず、「翻訳者として仕事を開始する日」を決めましょう。
そしてできる限り、その時の具体的な「あるべき姿」を数値化するほうが望ましいです。翻訳者であれば、例えば、どの分野で、レートいくらで、1日何ワード処理する、などです。
とはいえ、学習当初ではレートがどのくらいなのか、プロに求められるスピードがどのくらいなのか、自分がどの程度処理できるのか、まったくわからないことが多いでしょう。
プロに求められるレベルであれば、例えば、翻訳者・通訳者になる本のなどの雑誌や翻訳者・翻訳会社のブログなどに、プロに求められるレベルがどれくらいか、相場はどのくらいか、などが書かれています。
その他、例えば翻訳者ディレクトリなどの求人検索サイトでもおおよその情報はつかめると思います。
ただ、プロに求められるスピードやレートの相場がわかっても、自分の現状がわからないので、この時点で立てた目標は現実離れしているものになることも多いと思います。
それでも問題ありません。
まずは、「いつまでにどのような状態になっているか」を言語化して意識しておくことで、実際に訳してみて全く訳せないことがわかったときに、まず目標までの遠さに気づき、このままではヤバいと本気度が上がります。
そして学習が進むにつれ、自分のレベル(翻訳スピードなど)も数値化できるので、数値化した目標との差がわかり、強化すべき点が明確になってきます。
期限を決めて取り組む必要があるのは、「タイミングは今しかない」かもしれないから、という側面もあります。
2021年1月現在、コロナの影響で副業として翻訳業に参入しようと考えている方も増えています。新規参入はますます厳しくなるでしょう。
そして、自分自身を取り巻く環境も変化します。安泰だと思っていた会社が傾いてきたり、ずっと健康だった家族が病気になったり、自分自身が病気になるかもしれません。
私もそうだったのですが、そうは言っても「今目の前にない危機」を自分事ととらえるのはなかなか難しいです。
なので、期限つきの目標は周りの人に宣言するなり、ブログやSNSにアップするなりして自分にプレッシャーを与えたほうが成功しやすいのではないかと思います。
私は2年で思うような結果が出せずに、「あと1年で目標に届かなければきっぱり翻訳の道はあきらめる」ことをブログで宣言して、自分を追い込みました。
そこから実際に軌道に乗るまでの3か月ほどが、これまでで一番集中して学習した期間になりました。
2. 翻訳対象を訳すための学習に注力すること
特許翻訳の主な翻訳対象は、特許明細書と呼ばれる文書です。そのため、特許翻訳者を目指すのであれば特許明細書を訳すために必要な学習をする必要があります。
これは特許翻訳に限らず、医薬翻訳やその他の分野でも同じです。
こう書くとそんなの当たり前じゃないかと思われるでしょうが、「まずは英語の文法を完璧にしよう」とか、「まずは〇〇検定を受けよう」と思う方がかなり多いようです。
かくいう私も実はこのタイプで、翻訳の学習を開始する前に「まずは中国語検定1級を取ろう」(当時は中国語翻訳者を目指そうと思っていました)と思い、実際に取得してから、ようやく重い腰を上げて翻訳の学習を開始(講座を受講)しました。
これは本当に時間のロスでした。
1年早く始めていれば、今よりも1年分多くの売上と経験が得られていたはずだからです。
まずすべきことは、翻訳対象の文書について知り、その文書を訳してみてどの程度訳せるか、つまりゴールと現在地を確認することです。
訳せなければ、どこがわからなくて訳せないのかを確認し、その「わからないこと」をつぶしていくような学習をしていく、というのが大まかな学習プロセスになります。
特許明細書であれば、そもそも日本語のものを読んでも意味がわからない、ということに気づくと思います。そこでまずは日本語で読んで理解できるだけの知識を身に着ける必要があります。
と言うのは簡単ですが、ひとつひとつの明細書を読みながら「理解できるまで学習する」のはわからないことがあまりに多すぎて挫折しがちですし、効率もあまりよくありません。
例えて言うならば、「小さじ1杯」の意味もわからない人が料理人になろうとして、個別の料理の作り方を順不同にひとつひとつ覚えていくようなものです。
まず、料理の基本(例えば、調味料を入れる順番、下ごしらえ、火加減など)をマスターして、例えば、卵料理ならこういう作り方がある、とおおよそわかったうえで個別の料理を作りながら腕を上げていく方が断然効率もよく、応用が利くようになります。
特許翻訳に限らず、産業翻訳でこの「料理の基本」にあたるものは高校レベルの化学や物理の知識だと思っています。
私は今、主にバイオ・医薬関係の特許明細書の翻訳をしていますが、化学はもちろん、機械や電気の要素も出てきます。
その時に仮にわからないことがあったとしても、以前この基本の部分を学習していたおかげで、調査の時間を短縮することができています。
基本がわかれば、明細書を読むスピードも上がります。その状態から、ある分野の明細書を大量に読んでその分野で出てくる概念などをおおよそつかみます。
それから翻訳してみて、どこがわからないか、間違えたのかを分析して、足りない部分を補充します。
その過程で、「ミスしたのは文法の理解があやふやだからだ」ということがわかれば、文法をまず復習し、ミスした文と似たような翻訳対象文を検索して、理解ができているか確認します。
繰り返しになりますが「翻訳対象を翻訳する力をつける」ことを念頭において学習を進めることが大切です。
注意していただきたいのは「基礎が大切」と思って、翻訳するうえで必要のない部分まで学習を進めてしまうことです。
あまりここに時間をかけ過ぎると期限内に目標に到達するのが難しくなります。あくまで「翻訳に必要なレベル」にとどめておくことが必要です。
私はかなりやりすぎてしまい、目標からずれてしまっていました。
ただ、この「翻訳に必要なレベル」の線引きは、自分ではなかなか難しいところもあります。この辺りは、翻訳講座など第三者からアドバイスを受けた方が確実ではあると思います。
3. 語学力だけではなく総合的な「翻訳力」を伸ばすこと
翻訳には当然、語学力(外国語、日本語ともに)が必要です。
ですが、それ以外の要素も含めた総合的な「翻訳力」を伸ばしていくことが、翻訳者になるために、そして特に翻訳者として生計を立てていくために大切であると感じています。
この「総合力」には、例えば次のようなものが含まれます。
- 内容理解力
- ツール操作能力
- 営業力・マーケティング能力
- 自己管理能力
順番に説明していきます。
内容理解力
いくら外国語に精通していても、内容がわからないものは訳せません。
そのため実際の案件でも、翻訳する前にまず内容を把握するために調査をする必要があります。
ただ、納期の関係上、調査に十分な時間を取れない可能性が高いです。
もし希望する分野がある程度明確であれば、その分野の基礎知識を身につけた上で、その分野の関連書籍・資料を日本語でよいので日頃から読んでおくと、実際の案件に対応できるだけの内容理解力が深まっていくと思います。
特許明細書では、原文にミスがあることも多々あります(スペルミス以外にも、例えば、図面や他の記載箇所と矛盾した記載や常識的に考えてありえない単位など)。
内容を正確に理解して訳していれば、原文の矛盾も自信を持って的確に指摘することができます(翻訳会社やクライアントによっては、このコメント能力を翻訳者の評価の指標の1つにしているところもあるようです)。
ツール操作能力
ここで言うツールとは、TradosなどのCATツール(翻訳支援ツール)だけでなく、その他の翻訳に使用するツール(チェックに使用するツール、マクロの知識など)も含まれます。
CATツールに関しては、実務翻訳者になるのであれば個人的には「使用していると有利」ではなく「使用していないと不利」であると思っています。
その理由としては、発注側が「ツール使用可」である翻訳者を求めているということと、すでに多くの翻訳者が使用しており、「ツールを使用した作業スピード」が「プロの標準的な処理スピード」になっているのではないかと思うからです。
ここでは翻訳ツールの詳しい説明は省きますが(別記事:翻訳者がCATツール(翻訳支援ツール)を導入すべき3つの理由で若干説明しています)、基本的にワードベタ打ちよりも翻訳スピードが上がり、チェックも各種ツールで行えるので全体的な作業スピードは短縮されます。
仮にツール使用前提で平均処理ワード数2500ワードを求められる場合、自分がツールを使用しないことによって同等の処理量がこなせなければ、他の翻訳者との競争上不利になります(もちろん、依頼時に考慮される要素は処理ワード数だけではありません)。
また、翻訳の報酬は基本的にワード単価なので、作業スピードの向上は売上の増加に直結します。
そのため、少しでも早く翻訳作業が進むようにツールの使い方を見直したり、機械的なチェックに向いている項目はツールを使って省力化するなど、常に作業工程に改善できる場所はないか考えることが大切です。
なので、「ITは苦手で」「CATツールは高いし」と思うことは、自らを不利な条件に追い込んでいるのと同じです。
CATツールで効率化できた分、生産性は上がるので元はとれます。
ツールに関してもTradosなどのメジャーなものはネット上でいくらでも操作方法やトラブルシューティングの情報が見つかります。
私自身は、ツール関連は「翻訳ツール大全集」で基本的な操作を学んで、あとは自分でいろいろいじりつつ、わからないところは検索しつつで実務上は問題なく対応できるようになりました。
「翻訳ツール大全集」はこちらで少しだけ紹介していますが、これ以上にまとまった資料は他には見当たりません。
確かに掲載されているツールのバージョンは古くなっていますが、画面構成や基本の操作はそれほど変わっていないので今でも(2021年1月)十分参考になると思います。
ツールは触っていろんなエラーを経験してなんぼ、の部分もあります。
「IT苦手」は早いうちに克服したほうが後々絶対に有利です。
営業力・マーケティング力
トライアルに合格しても、仕事につながらない場合もあります。
それは、自身のレベルの問題もあるかもしれませんが、そもそも「その分野の案件が少ない」ことが理由であることも多いようです。
ニーズがなければ、自身の能力がどれほど高くても継続的な依頼は見込めません。需要がある分野を狙ったほうが参入しやすく、安定的な売上が見込めます。
求人情報などから、まずはニーズを探りましょう。
そして、「自分がやりたいこと、得意なこと」と「市場のニーズ」は必ずしもマッチしません。翻訳者で生計を立てていくことを考えているならば、ニーズに自分を合わせる方向で考えましょう。
さらに、積極的に動いて情報を取っていくことも大切です。
求人情報や雑誌などにも情報は載っていますが、自分自身が得た一次情報は何よりも貴重です。
自己管理能力
スケジュール・進捗管理
翻訳者になるまでには通常年単位の時間が必要です。そして結果が目に見える形ですぐに現れることもありません。
その中で着実に学習を重ねていくことは、「気合い」だけでは乗り切れない部分があります。
期限付きの目標を設定すること前提として、それに対して振り返って進捗状況を確認し、うまく進んでいないのならなぜかを考えて改善策を取っていく必要があります。
私は毎日、何にどれだけ時間を使ったかを記録していました。1週間で一区切りで振り返りを行い、今週できたこと、できなかったこと(解決すべき課題とその解決策)を考える時間を取っていました。
記録と振り返りに関しては、こちらの本が実践的で取り組みやすく、参考になりました。今でもこの本をベースとした記録と振り返りは継続しています。
次の記事でこの本を解説しています。
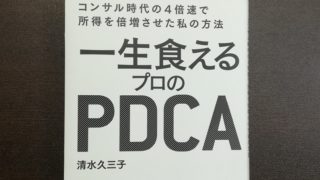
「自分自身を翻訳者にさせる」プロジェクトのマネージャーだと思って、ある意味自分を客観視して進めていければ理想的だと思います。
実はこの部分、私は当初まったくできていませんでした。なんでこれを間違えるんだろう、アホじゃないか、私にはやっぱり無理だ、とネガティブな感情に支配されて学習が進まなくなることもありました。
これはただの甘えであり、時間のロスでしかないです。
私がこの状態から抜け出るために一番効果があったのは、「今日やると決めたことを死守する」でした(学習に関係ないことでも。極端な話「ゴミ出し」などでも)。
どんなに小さいことであっても決めたことをやりきるのは達成感が得られるので、そこから次の行動につながりやすくなるのだと思います。
危機管理
案件を一旦引き受ければ、何が何でも納期通りに納品しなくてはなりません。
納品直前に限って、パソコンは挙動不審になります。実家から緊急の連絡が入るかもしれません。
データの多重バックアップ、別の場所でも作業できるような環境(ノートPCなど)の構築は普段から習慣にしておきましょう。
データバックアップは、BunBackupというフリーソフトが使い勝手がよくおすすめです。
「予備のPCはあるから最悪なんとかなる」と思っていても、定期的に予備のPCを使用していないと、いざ使う段になってメインPCで使っていたツールが入っていないのに気付いて真っ青になることもあります(経験談です)。
そしてもう一つ普段から癖づけておくとよいことは、自分の現在の処理スピードを把握しておくことです。
念願の案件を受注しても、キャパ以上の案件を請けてしまうと恐らくパニックになりますし、最悪納期の延長をお願いしなくてはならなくなります。
せっかく築き上げた信用も、失うのは一瞬です。
健康管理
目標を達成するために、時には睡眠時間を削ってぎりぎりまで自分を追い込む時期があってもよいとは思います。
ただ、睡眠時間は恒常的には削らないほうがよいです。明らかにパフォーマンスが落ちて、「パフォーマンスが落ちている」ことにも気づかない状態になります。
必要な睡眠時間(個人差がありますが、一般的には7時間くらいでしょうか)を差し引いたうえで、できる限りすべての時間を翻訳学習に充てましょう。
そして、翻訳作業に使用する設備・機器類(椅子、キーボード、マウスなど)は学習時からできるだけよいもの(プロが使用しているようなもの)を使用したほうが長い目で見て絶対に得です。体を痛めて稼働日数を減らしてしまったら元も子もないですから。
ちなみに、私が使用しているものは下記のとおりです。
実際、私も「マウスに3万は正直高い」と当初思いましたが、腱鞘炎になって病院にいったり数日業務が滞ることを思えば高くありません。
椅子:オカムラ シルフィ―
椅子は必ず試座しましょう。私は背もたれに背骨が当たって痛くなることがあるので、それを回避できることを最優先に選びました。3年ほど使用していますが、腰も背中も痛くなることがなく、クッションもへたっておらず快適です。
キーボード:東プレREALFORCE
「ずっとキーボードを打っていたい」感覚になります。キー荷重などでいくつか種類があります。私はこの写真のモデル(場所によってキー荷重が異なる変荷重タイプ)を使っています(変荷重であることを打鍵時に意識することはありませんが、打ちにくさはまったく感じません)。1日10時間以上の作業でも疲れません。
2025年追記:現在は東プレREALFORCEのR3HA23という機種を使用しています。キー荷重がすべて30gで、上記機種よりも軽いです。重めの打ち加減が好みでなければ、キー荷重は軽いほうがやはり疲れにくく、おすすめです。
マウス:ContourDesign RollerMouse RED
バーを左右に移動・上下に回転させて操作します。マウスクリックによる指の痛さとは完全に無縁になります。マルチディスプレイとも相性がよいです。操作には慣れが必要で、「合わない」といってやめる方もいますが、私は快適なので、しばらくこれを使い続けます。
まとめ
「翻訳者になるために大切な3つのこと」をお伝えしました。
- 期限付き目標を設定すること
- 翻訳対象を訳すための学習に注力すること
- 語学力だけではなく総合的な「翻訳力」を伸ばすこと
結果が出るまでにはかなりの時間がかかるのが普通です。
わかっていながらも、他人と比較して落ち込むことも普通です。
期限を区切って目標を定めて、そこに向けて毎日やることを決めてそれを実行・記録して、振り返って修正しつつ進めていく、という日々を積み重ねていくことができれば、ゼロからでも独学で翻訳者になることは可能だと思います。
と、書いている私はひとりではできなかったので、講座(レバレッジ特許翻訳講座)を利用しました。これまで書いてきたことも、講座で学習したことがベースになっています。
独学でできるタイプでも、外部の力を利用したほうが独学でやるよりも早くプロになれる可能性は高くなるのではないかと思います。
私は「レバレッジ特許翻訳講座」以外の翻訳講座の受講歴はありませんが、この講座はかなり独特で、向き不向きがある講座だと思います。
次のページに概要をまとめましたので、講座選びの参考になれば幸いです。


