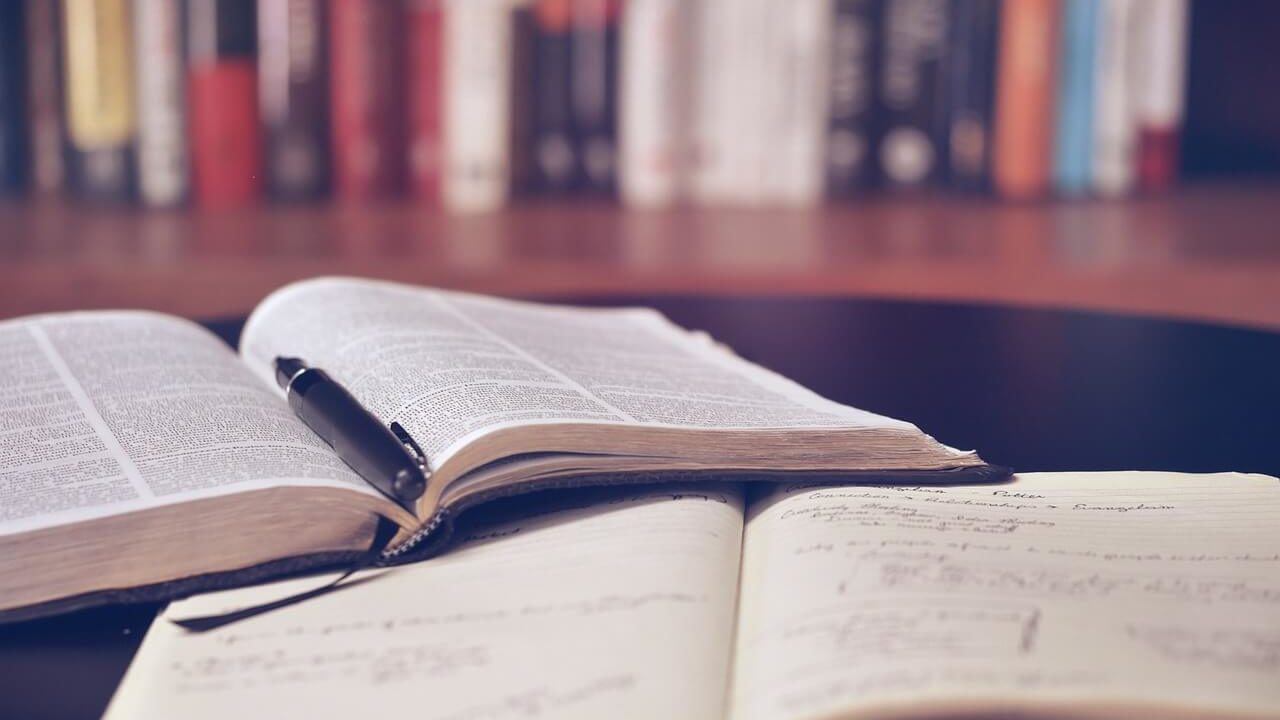限られた時間で最大の学びを得るために
今年に入ってから時間管理などいろいろと見直しているのですが、
その見直しの一環として、読書の方法も変えています。
なぜかというと、今までの読書の方法では
読みたい本がどんどん積みあがっていくだけで、しかも
読んでも読んだことに満足してしまって得るものが少ないのでは、と思ったからです。
ちなみに今までの読書の方法は、こんな感じでした。
これまでの読書スタイル
- 「読書の時間」をとって、基本的に1回で読み切る
- 始めから終わりまで読む
- 基本的に紙の本を購入し、赤線を引きながら読む
これを次のように変えています。
これからの読書スタイル(試行錯誤中)
- 毎日10~15分読書の時間をとる
- その本を読む目的を達成できるところだけじっくり読む(完璧に読もうとしない)
- 4色ボールペンで色分けしながら線を引く(線を引きすぎない)
- 途中でも本から学んだことをアウトプットする
(3)の色分けについてですが、こちらのpdf資料を参考にしました。
これはどこかのビデオセミナーで恐らく話があったと思うのですが、
残念ながらメモしておらず、どのビデオセミナーかわかりません。
隙間時間で見て、印刷だけしてそのままになっていたパターンです。
年末に資料整理をしている時にようやく「救出」されました。
引用の引用となりますが、下記の部分を実践しています。
私は自分が線を引くときには、三色ボールペンで色分けして引いている。青と赤が客観的な要約で、緑が主観的に「おもしろい」と思ったところだ。青は、「まあ大事」という程度のところに引き、赤は、本の主旨からして「すごく大事」だと考えるところに引く。赤だけ辿れば、本の基本的な要旨は取れるように引く。(以下略)(齋藤孝『読書力』(岩波新書 2002/09、140 頁)上記pdf資料のp.4-5より
今までは赤ペン一色で、とにかく「刺さった」ところに線を引いてました。
その結果、「赤ペン」だらけで何が本当に重要かわからない状態になっていました。
この色分け法を実践して、毎日読み進める前に本をパラパラとめくって
今まで読んだところの赤線部分だけ見るようにしています。
時間をかけずに本の内容を復習できるのでなかなか良いです。
もちろん、読んでいる時にも「これは赤線レベルかな?」と考えながら読むので
その面でも、漠然と赤ペンで線を引いていた頃より能動的な読書になっています。
このスタイルに変えてから1週間ほど経ちます。
本当に効果を実感するのはこれからだと思いますが、
現時点でわかったことをまとめます。
- 時間制限をかけると10分でも意外と読める(飛ばし読みで50ページくらい。もう少しスピードアップできそう)
- 色分け+アウトプット前提で読むと、常に「この本から何を学びたいのか」を意識するので得られるものが変わってくる
- 読書の時間がとても楽しみになる
「この本から何を学びたいのか」という目的意識を持つか持たないかで、
本当に読書に対する意識が変わります。
それから、毎日の読書タイムがとても楽しみになりました。
勉強時間は確かに減ります。
ただ、毎日の読書からは、かけた時間の何倍もの学びが得られると思います。
積読本の山は高くなる一方ですので、コツコツ読んでいきます。