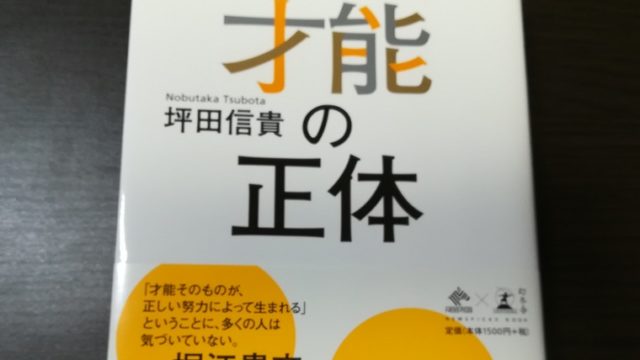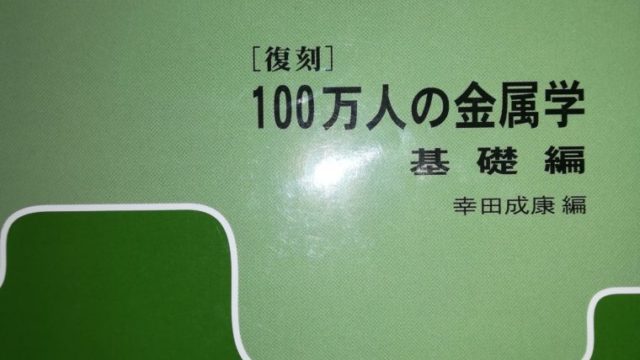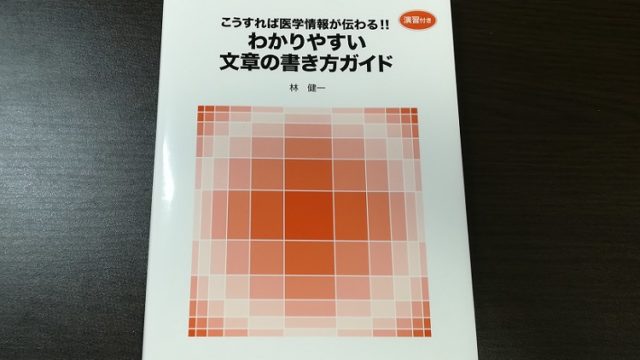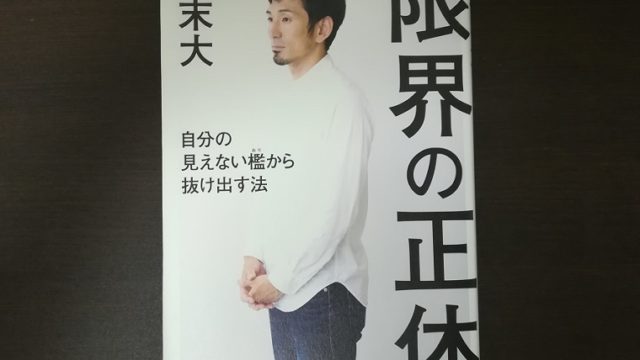私は翻訳会社を訪問した際、
「需要がありますよ」と言われた分野に、
「やらせてください!!てか既にやってますその分野。常識ですよ~」と言えずに
「どうしましょう」なんて管理人さんに相談したヘタレです。
このことについては本当に深く深く反省したのですが、
それ以外にも反省したことがありました。
それは、「まったく伝わらない報告書を書いていた」ことです。
今日は少しだけ、「進捗報告書とはどうあるべきか」について、
成果を生み出すテクニカルライティングという本の内容にそって、お話します。
Contents
そもそも、報告書を書く目的は?
報告書を書く目的って何でしょうか。
報告を受けた者が、一読して問題点(もしくは問題のないこと)を把握し次のアクションをとれる判断材料を提供するためです。
本では、報告書について次のように書かれています。
「報告を受ける側が報告してほしいと考えている内容を理解し、それを伝わりやすく端的に要約したもの」(p.108)
私は当初、訪問で得た情報をほぼ全て羅列した報告書を書いていました。
何か抜けがあって誤解があっては困るという気持ちからそうしました。
ですがこれは、情報の取捨選択をせずに、相手に判断を丸投げしている状態です。
(さらに言えば、一応要約はしたのですが、その「要約」に相手の判断材料となるであろう重要な項目が抜けているという罪な「要約」をしていました)
そんなこんなで当然のごとく「報告書のリライト」を命じられたのですが、
当初はまだ「私は全部書いたよなぁ、どうしたもんかなぁ」なんて思っていました。
そして、読もうと思って読んでいなかった「成果を生み出すテクニカルライティング」の存在を思い出し、進捗報告書の章だけとにかく読んでみました。
そこでようやく自分がいかにダメな報告書を書いていたかがわかったのです。
良い報告書とは何か
相手が一読して判断できる材料を、できるだけコンパクトに提供する。
これが良い報告書の肝です。
「相手が一読して判断できる」とは、
報告者がどのような背景の元に(背景・前提)、
どんな課題に直面していて・あるいはどんな課題を設定して(課題)、
それに対してどのようなアプローチを取って(手段・アプローチ)、
結果どうだったか、そして今後どうするつもりか(効果・結論)
がわかる報告書です。
自分の行動の根拠(思考の筋道)が言語化できている報告書、とも言えますね。
本ではこれを、黄金フォーマットと呼んでいます。
黄金フォーマットに当てはめてみてわかったこと
早速、この黄金ルールにあてはめて「訪問記録」をリライトしました。
背景・前提:
- トライアルに合格したが案件の打診がない
課題:
- 案件打診の可能性を高める
- 今後注力すべき分野を探る(一次情報の入手)
手段・アプローチ:
- 翻訳会社を訪問する
- 事前に想定問答集を作って練習する
- 翻訳会社のHPや求人情報などからニーズのありそうな分野を探る
- (訪問時)専門分野にこだわらず対応可であることを伝え、ニーズのある分野について聞き出す
効果・結論:
- 英日特許翻訳の需要は少ないので、ここにこだわり続けては案件打診の可能性は低い
- ニーズのあると言われた分野は今後も伸びていく。人手不足ならばレート、稼働率とも最大化できる可能性がある
- 案件が来れば内容問わず引き受け、この分野の学習を集中的に進める
私が今回の報告書で書きたかったことは、「ニーズのある分野へ切り込むこと」なので、それ以外の雑多な項目はバッサリ切り落としました。
ボリュームとして半分くらいになりましたが、伝わりやすくなったと思います。
そして報告書をリライトして気づいたことがあります。
ひとつは、この思考の枠組みを訪問前から意識しておけば
「得たい効果」をもう少し意識でき、もっと情報収集に貪欲になって、得られた結果が違っていたのではないかということ、
もうひとつは、訪問報告書を書く前に意識しておけば
論理的に考えることができ、「どうしたらよいでしょうか」なんて質問をすることはなかった、ということです。
まとめ
「書く」という作業には、それぞれ目的が存在します。
報告書であれば、「相手が一読して判断できる材料を、できるだけコンパクトに提供する」ことが目的です。
やったことをただ「絵日記」的に羅列しても、何も伝わりません。
黄金フォーマットを意識するだけで、ぐっと「伝わる」報告書になります。
是非、取り入れてみてください。
といいながら、私は実はまだこの本の一部しか読めていません。
また違う記事で、学んだことを書いていこうと思います。
2019/04/20追記:
第2弾です。テクニカルライティングがなぜ重要かについて書きました。