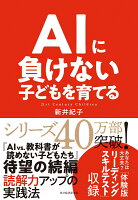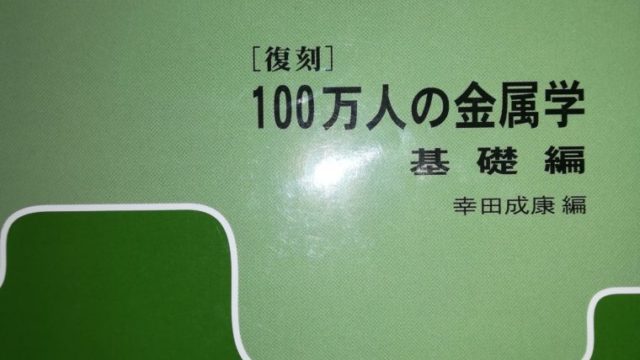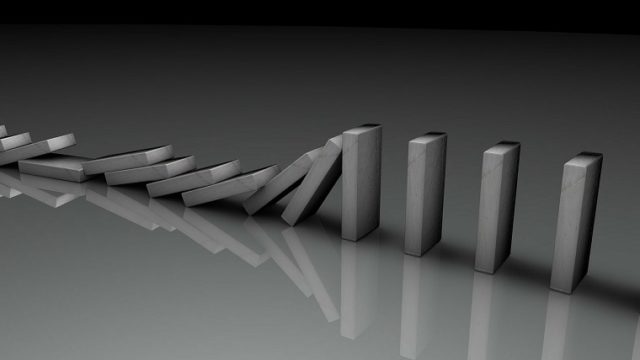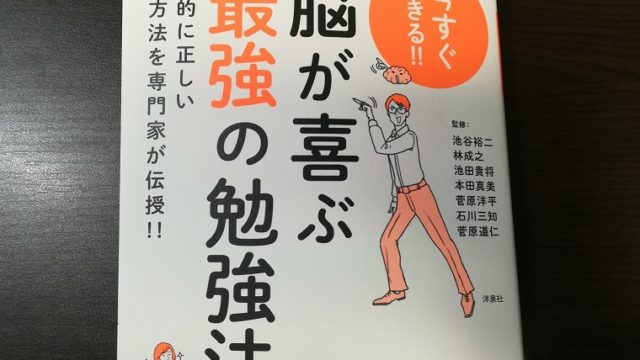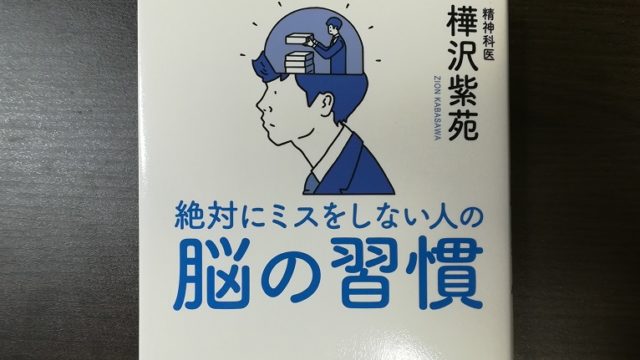「読解力」を身につけよう、というと子ども向けの話と思われるでしょうか。
実は大人も「読めているつもりで、読めていない」のです。
私も「読めているつもりで、読めていない」ひとりだということに最近気づきました。
「読めていない」ということは、日常生活全般に影響を与えます。
資料を読み間違えたり、仕事の生産性が上がらなかったりすることと関係しているからです。
逆に読解力を身につければ、文章を素早く読み取れる力だけでなく、状況を的確に判断する力やコミュニケーション能力をも高めることもできます。
読解力というのは、私たちの想像以上に大切なスキルなのです。
この記事を読んでわかることは、次の3点です。
自分の読解力の測り方
読解力を鍛えるメリット
大人の読解力の鍛え方
Contents
あなたは「読めて」いますか
読解力が大事だと言われても、まず自分がどの程度読めているのかがわからないことには始まりませんよね。
ここでは、「AIに負けない子どもを育てる」という本に付属の簡易的なテストと、私が受けてみた結果と感想をご紹介しつつ、「読めているつもり」がどういう状態なのかをお話します。
読解力診断テスト・RSTとは
読解力を診断するテストに、RSTがあります。
RSTはReading Skill Testの略称で、数学者で「ロボットが東大に入れるか」のプロジェクトを率いている新井紀子さんが開発したテストです。
文章の構造を正しく理解できているかを問う「係り受け解析」など、7種類の項目から読解力を診断します。
問題のサンプル、詳細は試験実施機関の「教育のための科学研究所」のサイトにあります(https://www.s4e.jp/example)。
上記のリンクからも受検はできますが、基本的に団体受検(20名以上)の受付です。
「代々木ゼミナール」にて日時限定で個人向けに行っているようです。直近では2020年2月のテストがあるようですが、残念ながらすでに締め切られています。
興味がある方は(https://www.s4e.jp/guidance-p)をチェックしてみてください。
次の本にRST簡易版が掲載されています。現状、個人が気軽にRSTを行うには、本を購入して簡易版を受検するのがベストだと思います。
簡易版とはいえ、7分野すべて網羅されていて、ある程度の傾向がわかるようになっています。
RSTテストの前にも、本の中にはいくつか例題が出てきます。
その例題は間違えることなく解けました。
それもあって、私は「こんなの間違えようがない」と思いながら、計28問の問題に解答しました。
ところが、その結果はとても衝撃的なものだったのです。
「自分も読めていない」という衝撃
恥を忍んで、私のRST診断結果を公開します。
問題は公開しませんので、気になる方は公式サイトの例題をチェックしてみてください。
7分野、それぞれ4問(1点、2点、3点、4点問題が各1問)です。
1. 係り受け 10/10
2. 順応解決 10/10
3. 同義文判定 10/10
4. 推論 7/10
5. イメージ同定 6/10
6. 具体例同定(辞書)4/10
7. 具体例同定(理数)6/10
ミスした問題数 計6問/28問中
実は2問ほど、「どっちだろうか」と迷った問題がありました。
そもそもそれを迷ってしまうのも問題なのですが、個人的に「え、自分、こんな間違いするの?」と思ったのが下記の3点です。
- 設問を読めていない(択一式と複数選択式の取り違え)
- 正しい答えを出しつつもメモ書きした内容を見誤る
- 答えを見ても、しばし「なんで?」と思ってしまった問題がある(問題の条件をきちんと読み取れていなかったことにあとで気づく)
この結果はとてもショックでした。
2問ほど悩んだ問題はあったけれど、それ以外は全部正解していると思っていたのです。
ふたを開けたらこの通りです。
「読めていない」ってこういうことなのか、と実感しました。
そして「読解力を身につけなければ」という危機感が生まれたのです。
RSTは総合得点の高低だけでなく、得点の分布傾向から受検者(団体)の特徴や今後の対策を考えるツールとしても有用のようです。
すでに11万人がRSTを受検しており、そこから得られた代表的なパターンについても、本の中で紹介がありました。
「前半(上記の1~3)は6点以上、後半(4~7)の2つ以上で3点以下」が「前高後低型」とされています。
これは、「この本を手に取る確率が最も高い層」であり、「活字を読むことは嫌いではなく知的好奇心もあるが、理数系には苦手意識がある」傾向があるそうです。
私は得点でみると厳密にはここには当てはまりませんが、「前半ができて後半ができない」のは確かですし、何より上記の特徴に当てはまります。
本によりますと、このタイプは論理と定義を理解する力が不十分であるため、数学が苦手です。
そして推論力が不足しているために、情報をインプットしてもそれを適切に判断できず、情報の海に溺れてしまったり(同調圧力に負けたり)、何かに感化されて猪突猛進したりといった非論理的な行動が目立つ、という特徴があります。
このあたりも思い当たる節があり、RST恐るべし、と思いました。
その他にも「全分野そこそこ型」などいくつかの典型例が紹介されています。
ちなみに「全問正解」は上位1%未満の読解力を有する人にあたり、生育環境にも影響があるとされています。
「AI読み」していませんか?
RSTテストの結果で衝撃を受けつつ本を読み進めると、「もしかしたらこれが読解力不足の原因なのでは」という記述を見つけました。
それが、「AI読み」をしている子どもが多い、という記述です。
「AI読み」とはAIが文章を「読む」時の読み方で、キーワードのみを捉えて読む方法です。
本には「徳川家光、参勤交代、武家諸法度、鎖国」という例が載っています。
なぜ家光が武家諸法度に参勤交代を加えたのか、その歴史的な背景などを読み解くことなく、「武家諸法度と言えば徳川家光で、家光と言えば鎖国」のように、「単語と単語のつながり」で暗記していれば、それはAIと同じ読み方といえるでしょう。
そして私は学生時代、おおよそこのような方法で暗記して乗り切ってきました。
そして、今でも同じようにキーワードだけを拾って、「キーワードを知っている」から「その文章を読めている」を勘違いしていることがあるのではないか、これが「読めているつもりで読めていない」正体なのではないかと思ったのです。
大人の読解力を上げることはできるのか
本では、中学・高校の偏差値とRSTの成績に高い相関があることが示されています。
その一方で、同じ中学・高校の学年間では成績にほぼ違いは見られません。
つまり、読解力は偏差値の高い高校に入ることで鍛えられるというわけではなく、読解力の高い学生(RSTの成績がよい学生)が、偏差値の高い高校へ入学できるという事実を示しています。
本では小学校の授業を改善して、子どもに読解力を身につけさせる実例とその成果が記載されています。
読解力の有無で将来採りうる選択肢の幅が変わるのですから、子どもに読解力を身につけさせることはとても大切です。
一方で、大人の読解力はどうすれば上がるのでしょうか。
そもそも、高校でほぼ変わらなくなっている読解力を、大人になってから伸ばすことができるのでしょうか。
大人が読解力を上げることは可能です
AIに負けない子どもを育てるの最後の章に、「大人も読解力を上げるのは可能」という実例が紹介されています。
ここまで本を読んで、自分が「思ったより読めてない」ことにショックを受け、そして「読解力がないことで起こること」に危機感を抱いていた私にとって、最後の章で救われた思いがしました。
この章で紹介されているのは、当初RSTの問題が解けなかった30代後半の男性が、RST問題のレビューを半年ほど真剣に取り組んだことで、読解力が飛躍的に伸びたというお話です。
どのような取り組み方をされていたのかについて、引用します。
それまではエクセルシート上で行っていたレビュー作業をやめ、1問ずつ印刷し、提示された文章を丁寧に読み、そこに出てくる単語や助詞の働きについて正確に吟味し、わからないことは辞書を調べながらレビューを行うことにした
(AIに負けない子どもを育てる p.312)
さらに、レビューをしている関係上、作問者にフィードバックを行うこともあります。その時にも、「なぜこの問題はNGなのか」を相手が納得するように文章で伝えなくてはなりません。
基本にかえって、1文1文じっくりと正確に読む訓練をすること、そして相手に自分の意思を正確に文章で伝えること。
文章で書いてしまうと簡単ですが、ご本人は相当な努力をされたのだと思います。
それでも、「大人になっても読解力は向上する」という事実に勇気づけられ、読解力向上を目指そうという強い動機付けにもなりました。
しかもこの方は、読解力が向上したことで書くスピードも上がり、さらに他分野の方と仕事をするなど、業務遂行能力が向上し、仕事の幅も広がったそうです。
読解力があれば、未知の分野の文章も正確に読めるようになり、情報を正確に読み取り自分の中で操作することで、正しい判断も下せるようになるのでしょう。
まさに「読解力がすべての能力の土台である」と言えますね。
読解力を上げる方法とは
読解力を上げる方法として、RSTを1問1問吟味してレビューすることが有用だったというエピソードをご紹介しました。
ただ、「RSTのレビュー」というのはかなり特殊な作業です。
私たちが読解力を上げるには、どんな方法が有効なのでしょうか。
そのヒントが、「頭がいい」の正体は読解力という本にありました。
この本でおすすめされている読解力向上の方法、それは「書くこと」です。
本ではサッカーをより深く理解できるのは、サッカー経験者であることを例に挙げて、「実際に書いてみることではじめて文章を理解でき、その結果として読解力も上がる」と書かれています。
この本は練習問題が全体の3分の1ほどを占めていますが、うち「書く練習」が半分以上となっています。
練習は一言でいえば「言語運用力」を高めるための練習です。
具体的には、言い換えの練習(抽象的なものを具体的に、文を分ける・つなげる、婉曲表現に変えるなど)と要約の練習などです。
実際に練習問題を解いてみて、思いのほか言い換えがスムーズに出てこないことに気づきました。
細かな練習項目についてはここでは記載しませんが、本の中でおすすめされている「書く力」の鍛え方は、次の2点です。
- 小論文を書く
- 要約を書く(読後感など)
そして、常に別の表現がないか考えることが大切だとされています。
小論文については、論理的な文章の「型」を学ぶことができ、読む時に文の構造を考えることにつながります。
要約については、先ほどの「AIに負けない子どもを育てる」にも登場していましたので、やはり書く力・読解力の向上には効果があるといえそうです。
ブログなどで、読んだ本や記事の感想をアウトプットすることも要約の練習になりますし、長く書くことでも書く力の訓練になります。
私たちが気軽に、継続して取り組むにはよい方法なのではないかと思います。
本では、書くことで文章を自分のものにする練習を行ったあとで、最後に「読む方法」について(キーワード、主張などに絞って読んだり、文章の骨格をつかむ読み方)を紹介しています。
「読む方法」にも練習問題がついているのですが、最後の問題(ある大学入試の問題)は非常に難しく、実を言うと途中でついていけなくなりギブアップしました。
書く力を鍛えて、時間をおいて読めるかどうか、再挑戦してみたいと思います。
まとめ
「読解力」はすべての能力の土台となります。
1文1文にじっくりと向き合うこと、そして書くことを通じて読解力を高めることができます。
「私は読めているから問題ない」と思われる方は、一度本の簡易版RSTでテストしてみることをおすすめします。
もしかしたら、あなたも読めていないのかもしれません。
「AIに負けない子どもを育てる」で私が深く納得したのは、次の文章でした。
(抽象概念を理解し、操作することから子どもたちが逃げないように心掛けるのはとても大切、という趣旨の文章からの続きで)
なぜなら、現代社会で生き残る上では、意味を理解しながら抽象概念操作ができることは圧倒的なパワーを意味するからです。 (p.199)
大人が今までの「読み方」から脱却するのはとても大変です。
ですが、AIに代替されない人間であるためには、「文章を正しく読めて、それを運用できる」力が必要なのです。
「読める」か「読めない」かで、これからの人生が左右されるとしたら。
今からコツコツ、読解力を鍛えていきたいですね。