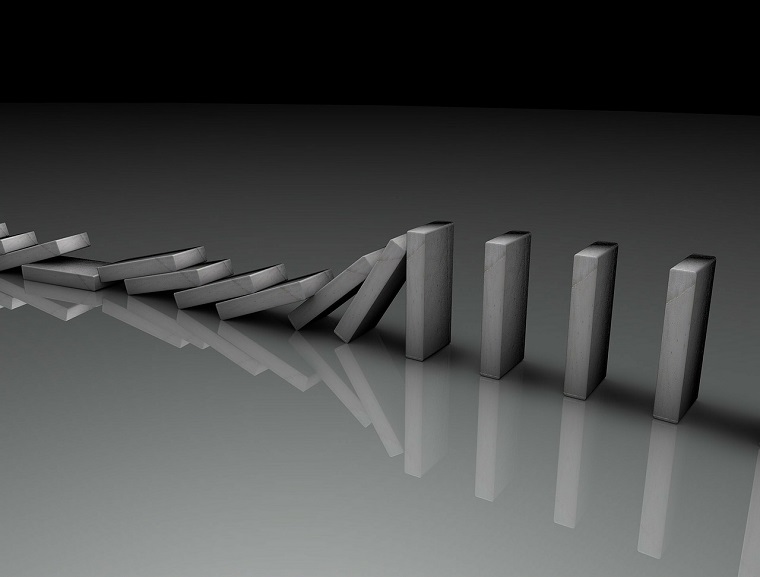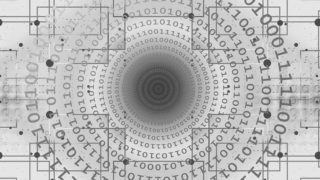学習記録
黒字が予定、青字が実績です。
翻訳を完了させる(残り1700wほど、請求項メイン)+ペンディングにしている部分を見直し、確定、チェック作業へ。
- 翻訳 (9559w/9559w・終了 本日+1693w )
- チェック 進捗15%くらい?
- 学習予定時間:15時間→15時間+1時間弱Tradosトラブルと格闘
抗体医薬関連の明細書の翻訳を進めています。
今日は訳し終わってチェック作業に入っています。
今日の要改善項目は、翻訳時に用語の揺らぎや、日本語がしっくりこないところ、「多分こうだと思うがあとで念のため確認」以外の部分でなるべくペンディングしないようにする、ということです。
今日は最後に訳す請求項部分に入る前に「後で確認」にしておいた部分を見直したのですが、そこで3時間ほどかかりました。
中には、「あー、まあこれは確かに後でわかるからペンディング扱いで正解だったな」という部分もありました。
ただ、それ以外に明らかに(恐らく眠かったか疲れていたかで)「今はちょっとしんどいから後でちゃんと確認しよう」としていた部分がありました。
その判断もありといえばありなんですが、もう一度調べるにも余計に時間がかかりますし、何より予想以上にこの確認に時間がかかったので、スケジュールが押してしまう原因になります。
今朝の「受講生ブログへのコメント」で今の段階でスピードにこだわる意味はあまりない(計測は必要)とコメントをいただきました(+その他いろいろ)。ありがとうございました。
訳すスピードが遅いということに問題意識があったのと、数字で見えるので客観化できるという意味もあって、レベルアップの指標として使っていました。
ただ、「純粋な翻訳時のスピード」だけ測っても意味はないなと改めて気づきました(もちろん、調査やチェックの時間も計測しています)。
翻訳時に曖昧にしている部分が多ければ、当たり前ですがチェックでそれだけ時間がかかります。
・・・といいつつ、「とりあえず仮決めで、確定は後にしたほうが結果的には早いだろう」という部分も確かにあります。
翻訳作業のスピードにこだわるのではなく、背景を素早く読み取ること、チェックを最小限の時間でミスなく終わらせることなど、これらもひっくるめて全体として最適化していくにはどうしたらよいか、を考えなければならないですね。
何とも抽象的で当たり前なことばかり書いてしまいましたが、今日はこれにて。
2/19の予定
チェックを進める(最終チェック(もう一度通して黙読する)前まで)
学習予定時間:15時間