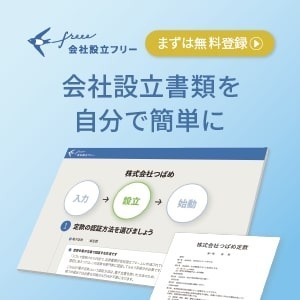こんにちは!
2020年度分の確定申告を終えて、テンションが上がっております!
普段、語尾に「!」なんてつけないんですけど!!!
確定申告は2度目ですが、今回はじめて青色申告しました。
「青色申告って圧倒的にお得だとは聞いてるけど、なんか難しそう。私にできるだろうか・・・」
と、正直かなりビビっておりましたが、杞憂でした。
拍子抜けするくらい簡単でした。
ただ、「会計ソフトを使用したら」という前提があります。
なので、今回は下記のことをお伝えしたいと思います。
- 青色申告は絶対にすべき
- 会計ソフトは導入すべき
- 早め早めに確定申告に向けた準備をすべき
Contents
青色申告とは
青色申告とは、ざっくり説明すると
「複式簿記で記帳して、帳簿を所定の期間保管して、確定申告の際に必要な書類を出せばいろんな優遇措置が受けられますよ」
ということです。
優遇措置のうちのもっとも大きなものは「65万円が課税所得から控除される」というものです(2020年度分から、電子申告の場合のみ適用。それ以外は55万円の控除です)。
控除によって課税所得が低くなるため、所得税が安くなるわけですね。
控除できるものは他にもいろいろとありますが、青色申告を選択するだけで65万円の控除は本当に大きいです。
青色申告は、「事業所得や不動産所得のある事業を営んでいること」が条件になるので、開業届を提出して個人事業主になり、かつ「所得税の青色申告承認申請書」を提出すれば青色申告の選択が可能になります。
少し余談ですが、会社員から失業保険受給を経て個人事業主にシフトするときには、「開業届」を提出してしまうと「失業状態」とみなされず、原則として失業保険の給付の対象外になってしまうので、開業届の提出のタイミングには少し注意が必要です。
青色申告であれば赤字を3年間繰り越せるので、失業保険の受給額よりもトータルで割りに合えば、失業保険の受給権利を放棄してすぐに青色申告を申請するのもありかもしれません。
私は、失業保険の受給が終わってから開業届を提出しました。
後述しますが、開業費として開業までにかかった費用をプールしておけば、「赤字の繰り越し」と同じような効果が得られると思ったからです。
青色申告の優遇を受ける条件については国税庁のサイト(No.2072 青色申告特別控除)をご覧ください。
青色申告の優遇の詳細については、青色申告と白色申告は何が違う?メリットとデメリットとは(freee)に詳しいです。
開業届のタイミングについては、開業届のデメリットとは?副業、扶養、失業保険など注意が必要なケースを解説(freee)に詳しいです。
青色申告は、会計ソフトを使えばまったく難しくない
青色申告の優遇を受けるには、複式簿記で記帳して、
- 確定申告書B
- 青色申告決算書(貸借対照表など4枚で構成)
の2種類の書類を提出する(65万円控除であれば、電子申告する)必要があります。
これを自力でやれと言われたらかなり大変ですが、会計ソフトを使用すればあっという間に終わります。
というのも、会計ソフトは、
- 日々の取引を記帳すると(複式簿記の知識は不要です)、
- 記帳した内容から確定申告で提出する書類を作成してくれて(ガイドに従って控除金額などを記載するだけで作成完了です)
- e-taxと連動したアプリでそのまま電子申告(マイナンバーカードが必要。これはもしかしたら使用する会計ソフトによって異なるかもしれません)
ができるからです。
私は会計freeeという会計ソフトを使用していますが、おそらく評判のいい会計ソフトであれば、どれも似たような機能なのではないかと思います。
会計ソフトには、大きくわけてクラウド型(使用料を払う形のもの。freeeはこちらのタイプで、一番安い個人事業主用プランで税込で年12,936円です)とインストール型(買い切り型)があります。
どれがおすすめかは、検索するといろいろ出てきますので調査してみてください。
私がfreeeにした理由は、「評判が良いし、ヘルプもしっかりしている(更新日が新しい)」というかなりぼんやりとした理由でした。
あとは、クラウド型のほうが税制改正への対応がスムーズだろうな、ということも考えました。
他のソフトを使用したことがないので比較はできませんが、実際に使用してみた感想としては、
- 操作がわかりやすい(簿記の知識がいらない。もちろんわからないことは都度調べる必要はありますが)
- ヘルプページで解決できないことはほぼない。一度だけヘルプページで解決できずにチャットで対応いただいたがそれほど待たなかった(これは時期によるとは思いますが)
といったところでしょうか(PC版を使っています。スマホで確定申告も可能です)。
ランニングコストがかかるのは難点ですが、日々の記帳をサポートしてくれて、何より確定申告をここまで楽にしてくれるので、月1000円の価値はあるかなと思っています。
初めての青色申告。やってよかったこと、やるべきだったこと
青色申告を終えて、「やっといてよかった」と思ったこと、「やっておくべきだった」と思ったことをまとめます。
今後個人事業主となる予定の方、青色申告への切り替えを考えている方の参考になれば幸いです。
やってよかったこと
その1. 開業費の計上
開業まで(開業届を提出するまで)に、その事業に関連してかかった費用は開業費という資産の科目に計上することができます。
そして、この開業費は、5年間で任意償却(毎年好きな金額で経費化)できます。
その年の収入に応じて、「今年は売上が多かったから多めに償却しよう」など、支払う税額を調整するのに有効活用できます。
その2. 国民年金の免除申請(2019年度)→2年分まとめて支払い(2020年度)
国民年金の支払額は、所得から全額控除されます。
2019年度は、会社を退職した年で売上も数十万円程度でしたので、国民年金の免除申請を行い、2020年度に2年分を支払いました。
2020年度で控除できる金額を増やしたかったのでこのようにしました。20万円程の差ですが、これは2020年度にもってきてよかったと思っています。
その3. 個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入
2020年度の途中からiDeCoへ加入しました。
iDeCoの掛金も全額所得控除です。今年の掛け金としては20万円ほどですが、やはりインパクトはあります。
その4. 事前に税金についてある程度学んだこと
知識がある状態とない状態では減らせる税金の額はかなり変わったと思います。
初心者向けの本はいろいろありますが、大体同じことが書いてあるので評判のよいものを数冊読めば十分だと思います。
一冊挙げるなら、有名どころですがやはりこの本がおすすめです。
漫画形式で読みやすく、最低限必要な情報は網羅されていると思います。
この本に登場する税理士の大河内薫さんのYouTubeチャンネル(税理士大河内薫の税金チャンネル)もおすすめです。
やっておくべきだったこと
次に、やっておくべきだったなー、と若干確定申告の段になって後悔したことを挙げてみます。
その1. 開業費の計上は計画的にすべきだった
「やってよかったこと」に書いた開業費の計上、実は開業してからまとめました。
領収書の類いは取ってあったのですが、ないものもあったり記憶も薄れていたりして、口座とクレジットカード、アマゾンの購入履歴などを見ながら付け合わせてなんやかんやで1日仕事でした。
おそらく、取りこぼしもあると思います。
開業費は勘定科目ごとに分けたりする必要もないので、都度(月1でも)Excelなどでまとめていくことをおすすめします。
その2.帳簿付けは計画的にすべきだった
これも、その1.と根っこは同じですね。
途中までは、月1回(毎月10日前後)を作業日と決めていたんですが、1ヶ月後回しにしてしまったらその後ずっと後回しにしてしまい・・・
その結果、確定申告の際に4ヶ月まとめて記帳する羽目になりました。
「確定申告の時にまとめてやる派」もいらっしゃるかもしれませんが、個人的には月1とかで都度片付けたほうが断然よいと思っています。
理由としては、ひとつは先ほどと同様「忘れやすい、漏れが発生しやすい」からです。
そしてもうひとつは、「確定申告」への心理的ハードルが上がるからです。
「あれを全部記帳しないといけないのか~」と重い腰を上げつつやることになります。
逆に、毎月きちんと記帳できていれば、年次処理のみで済むのでささっと申告を終わらせることができ、仕事のスケジュールにも響きません。
その3.その他の節税手段をもっと使うべきだった
具体的には、ふるさと納税、小規模企業共済です。あとは、課税所得から控除されるわけではないですが運用益が非課税になるのが魅力な(つみたて)NISAですね。
これらもお得だな、やらなきゃなと思いながら、何にどう資産を振り分けようか(やりすぎても、他に投資できる手元の現金が減ってしまうので)考えているうちに放置していました。
iDeCoや小規模企業共済などは、本質的には老後資金のための投資で節税を主目的にするものではないのかもしれませんが、それでも特に個人事業主にはかなりお得な制度だと思います。
このあたりに興味のある方は、さきほどご紹介した大河内薫さんのYouTubeチャンネル(税理士大河内薫の税金チャンネル)に最新の情報がわかりやすくまとまっているのでチェックしてみてください。
まとめ
初めての青色申告が無事に、そしてあっけなく終わったうれしさで書いてきました。
青色申告は最大65万円の控除、そしてその他の優遇措置も強力なので選択しない手はないです。
青色申告には、決まった書類を提出したり、複式簿記で記帳したりしなければならないというルールがありますが、それらは会計ソフトを使用すれば会計の知識がなくてもクリアできます。
ぜひ、青色申告を検討してみてください!