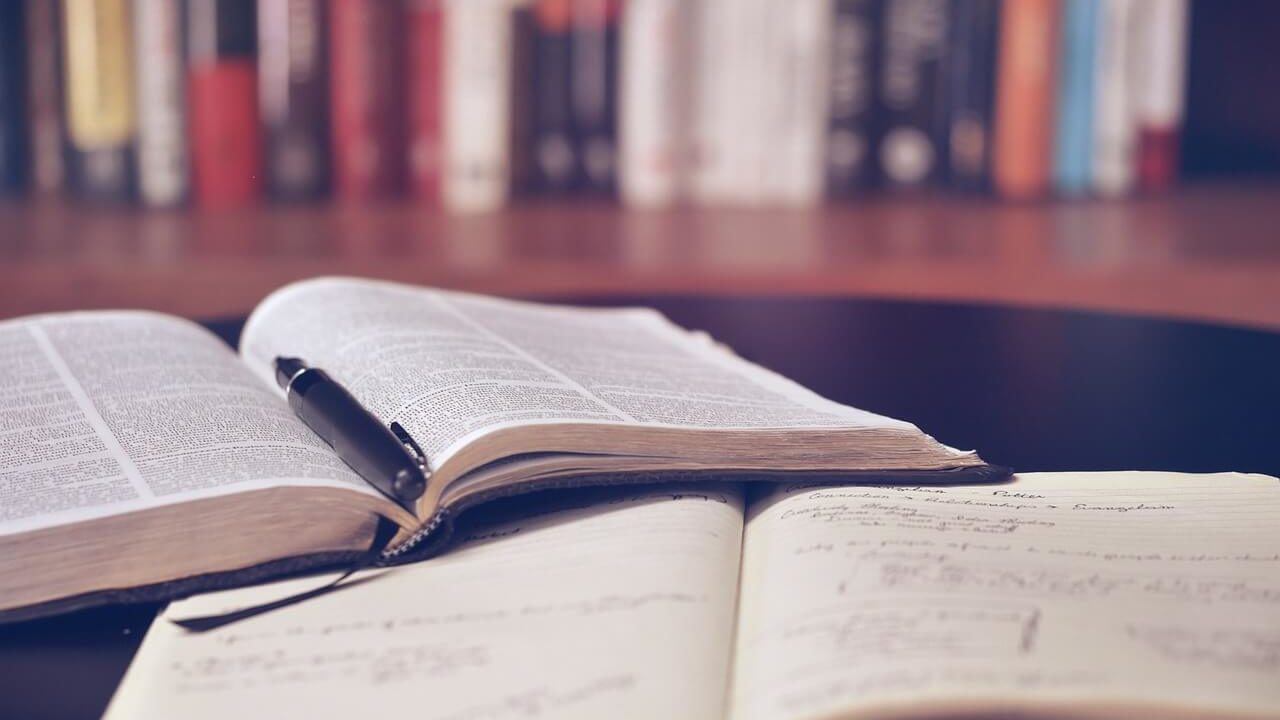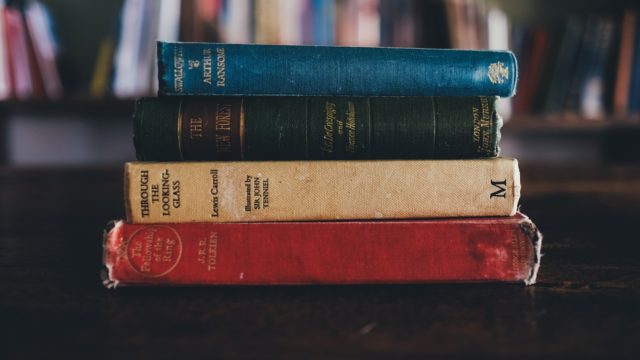昨日心の中でぐるぐるっとしていたもの。
それは今後の学習の進め方についての不安と迷いでした。
だいぶ細い所に入り込んで抜け出せなくなってしまったので、これ以上考えていても仕方ないと思い、管理人さんに相談しました。
質問の際に、「~と考えてますが、この方向性であってますか」と、
またも「答え」を求めてしまっていました。
(4か月目に今後の方向性について聞いたときも、全く同じ聞き方をしていました。成長の2文字が遠い・・・)
自分でぐるぐると考えている時に、もはや何度目かわかりませんが講座案内の受講感想を読み直していました。
もちろんとても参考になるのですが、自分とまったく同じ環境で同じ目標を持った方がいるわけもなく、仮にいたとしても当時と今とでは外部環境が変わっているわけで、そこにヒントはあれど「答え」はありません。
なぜすぐ「答え」を求めてしまうんだろうな、と少し考えました。
結局は自分で選択する能力と覚悟がなく、他人に判断してほしいという甘えた気持ちなんでしょうね。
講座でもよく言われてますが、何かを選択することは何かを捨てることです。
何かを捨てるって、意外と難しいです。
まず、優先順位をつけなくてはいけません。
そして、捨てたら後悔するんじゃないかという貧乏根性を、それこそ捨てなきゃいけません。
で、捨てられないから、選択できない、決断できない。
ではなぜ捨てられないのか、優先順位がつけられないのかというと、目的が見えていないからでしょうね。
またちょっと変な例ですが、お昼の時間が5分しかない、でも朝も食べてないからなにか食べきゃまずい、となった時に食べるものって大体限られてきますよね。おにぎりとか。
どんなに誘惑に駆られても、そこでラーメン屋の行列に並ぼうという選択肢はないでしょう。
勉強に当てはめてみれば、
まず自分の目指すべき場所がどこなのか、
いつまでにそこに到達しなきゃいけないのか、
今やっているこの勉強は何のためなのか、
そこをきちんと把握することで、確信を持って今何をすべきか、すべきでないかが選択できるんだと思います。
長々自分に言い聞かせるように書いてきましたが、そうした確信を持った行動の結果こそが、答えなんだと思います。
なので、行動しなきゃ答え=結果は見えないんですよね。
で、さらに戻りますが、行動のためには目標が必要だと。うーん、あまりに当たり前な話でした。ここまで書いておいてなんですけども。
肝心の学習の方向性についてですが、向こう1年間くらいの螺旋階段を登っていくイメージを自分の中で持つことができました。
時間の関係でまだ書いていませんが、今日必ず紙に時系列で到達しているべき状況を書いて貼り付けておきます。10年手帳にも1年目以降のあるべき姿を含めて、書き込んでおきます。
「8か月目の今、どこに立っているのか、
どこに立っているべきだったのか考えているか」
これが、一昨日のビデオセミナー2728号でブログに対していただいたコメントです。
期限内に結果を出す。そのために目標設定する。現時点との差を見つめて、軌道修正する。
何度も講座で言われている基本的なことですが、疎かにしていました。
今回、この大切さを以前より深いレベルで実感しました。
まだまだ先が見えない状況ですが、自分を信じて、自分の決めた方向へ進んでいきます。
8/24(金)の学習記録
学習時間:1h40m
項目: IBM社レジスト特許を読む(37)途中から
目標: 3h 実績: 1h40m
項目: 振り返り、学習進捗状況レポートの作成など
目標: ― 実績: 4h20m
8/25(土)の学習計画
項目: IBM社レジスト特許を読む(37)途中から
目標: 15h30m
項目: 今後の目標を紙に時系列で書き出す。10年手帳に書く
目標: 30m