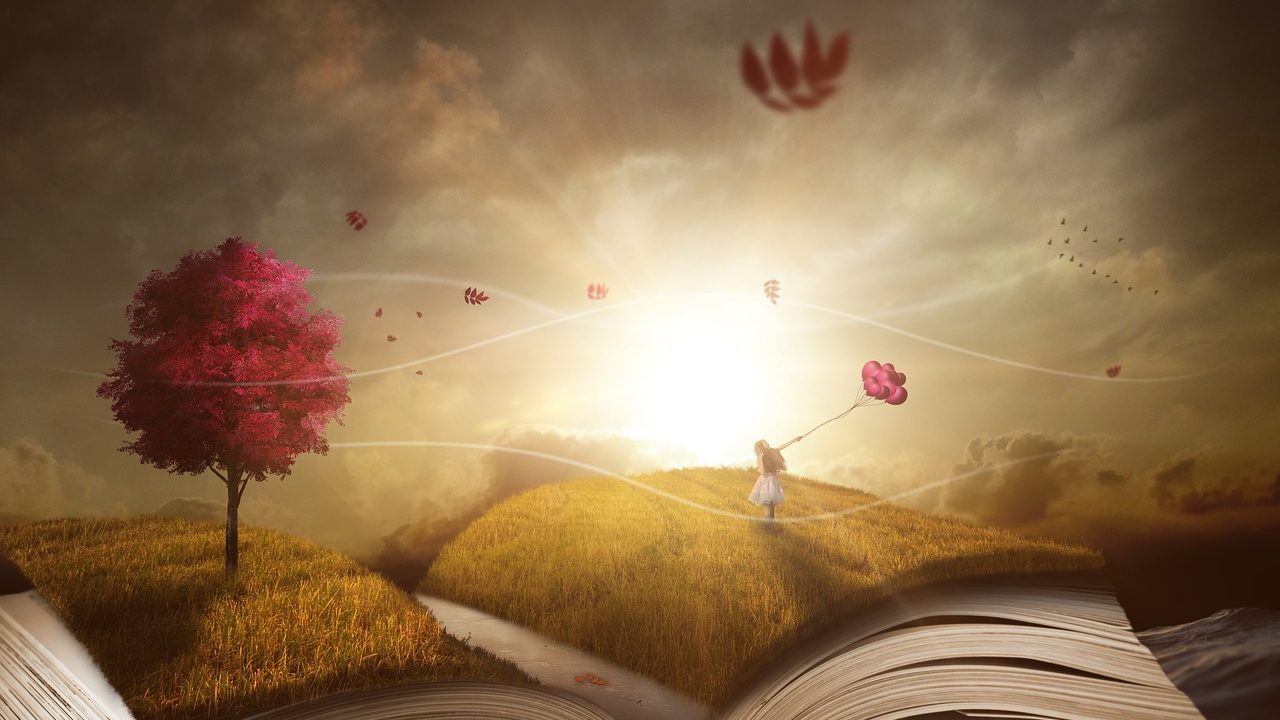「かえし」付きの釣り針
今日は久々に、読んだ本について思うところを書きます。
だいぶ前の記事で少し触れてはいたのですが、
ずっと書くタイミングを失っていた「英雄の書」を取り上げます。
恐らく、本を読んでも同じように刺さる人と、
それほどでもない人がいると思います。
なので、私の「えぐられポイント」を本から少し引用します。
- 「できない、できない」と騒ぐ者ほど、実は傲慢なのだ。(p.18)
- 何かに挑戦する前に、うまくいかないことを数え上げないこと(p.36)
- 幼少期に「失敗」を回避した脳は脆弱である(p.38)
- 思春期に「失敗」を回避した脳は人生が他人事になる(p.47)
- 「他人の思惑を気にする人」は、結局のところ、ただの「自分思い」なのだ(p.85)
いかがでしょうか。
ポイント高かった方、ぜひお読みください。
私はもちろん(?)、満点でした。
本のタイトルからは、結局何を書いた本なのか見えてこないかもしれませんね。
自分が自分のための英雄となって、人生を切り開いていく。
そのためには、自尊心と使命感を持ち、失敗を恐れないこと。
その具体的な方法について、人工知能の研究者でもある著者が
脳科学の見地と自らの経験からひも解いている本です。
ここでは「失敗」との向き合い方をメインに、
本の内容、自分の感じたことを書いていきたいと思います。
成功につながる「失敗」とは
みなさんが、「失敗した~」って思うときって、どんな時でしょうか。
そして「失敗した」という「事実」とどう向き合いますか。
「あの時、一言言っておけばよかったな」
「なぜ同じ失敗ばかり繰り返すんだ。なんてダメなんだ私は」
「いや、でも私は言われた通りにやったし仕方なかった」
「失敗したな」と思った時、
私の頭の中は大体こんなセリフで埋め尽くされています。
本の中で、脳が進化するには「失敗」が不可欠だと説明されています。
とは言え、そこには脳の進化につながる「失敗」と、
かえって次の失敗を呼び込んでしまう「失敗」とがあります。
その違いは何でしょうか。
本では、脳は電気回路のようなもので、「失敗」を経験すればするほど
「失敗」につながる回路には電気信号が流れにくくなるために、
失敗しにくくなる、つまり成功に繋がりやすくなると書かれています。
なので、失敗回路を断ち切るような「失敗」をすることが大切と言えますね。
失敗回路を断ち切るためには、次の3つのことが大切です。
- 「失敗」を誰のせいにもしないこと
- 過去の「失敗」にくよくよしないこと
- 未来の「失敗」におどおどしないこと
●「失敗」を誰のせいにもしないこと
失敗を自分事ととらえず、どこか「他人のせい」にしているとどうなるでしょうか。
そうすると、脳は自分が失敗したと認知しないので、失敗回路はそのまま残ります。
逆に、他人の失敗も自分の失敗と捉えることができれば、
そこから失敗回路を切り捨てることができます。
つまり、他人の失敗から学び、自らの成功に繋げていけるということですね。
●過去の「失敗」にくよくよしない、未来の「失敗」におどおどしない
これは一言でいえばネガティブ思考は捨てましょう、ということです。
過去の失敗を思い出しては「できない自分」を認識する。
未来に起こり得る「失敗」を想定して「きっと失敗するだろう」と心配する。
これらは失敗回路に電流を流して、失敗回路を活性化させているに過ぎません。
そして私は、これまでせっせと「失敗回路」を活性化させてきました。
「失敗回路」を断ち切って「成功回路」を強化しなくては。
ネガティブ思考から本気で脱却しなければ、成功はない。
このことが、この本から得られた一番の気づきです。
私の「ゆるせない」こと
この本は、「失敗の章」の後、
「孤高の章」「自尊心の章」「使命感の章」「贐の章」と続きます。
それぞれ、紹介したいことがいっぱいあります。
ここではかなり個人的な話になりますが、
「そうだったのか!」と腑に落ちたことをひとつ、書いておこうと思います。
「自尊心」の章には、
スカートの丈にこだわり続けたココ・シャネルや
フォントにこだわり続けたスティーブ・ジョブスのように、
自分の世界観において「ゆるせないこと」を見つけましょう、と書かれています。
「ゆるせないこと」か。何だろうな。
受け身な人生を送っていると、
「自分が何が好きか」「何がゆるせないのか」という
自分の持っている判断基準や方針すらも見えなくなってしまいます。
この章で著者のこんなエピソードが紹介されています。引用します。
私自身は、14歳の時に、「依存」を嫌悪した。私があまりにも生意気だったのだろう、父が「誰のおかげで食えてると思っているんだ」と叱責したことがあったのだ。(p.99)
著者はこの時に父親に反論できず、自尊心を傷つけられたと述べています。
そしてこの時に、「自分の食い扶持は何があっても自分で稼ぐ」
と心に決めたと書かれています。
これを読んだ時、はっとしました。
なぜなら、私にも全く同じ経験があるからです。
その時に私も、
「絶対に高校卒業したら親に経済的な援助を求めない」と決めました。
大学時代はアルバイトと奨学金で賄い、
大学の入学当初の費用は負担をしてもらいましたが、それも後で返しました。
この言葉が私にとっては「ゆるせないこと」で、
その後の行動を決めていたんだなということに気付きました。
今も「年を取っても経済的に自立した人生を送るため」に
頑張っているわけですから。
確かに、比較的早くから経済的に自立してきたことは自分自身の中では
「小さな自信」であり、「成功体験」でもありました。
でも、こうやって外からの刺激で気付くまで、気づいていませんでした。
自分の軸なんてないと思っていた私にも、一応軸はあったんだな、
「ゆるせないこと」を持って行動するってこういうことなんだなということが
今回腹にすとんと落ちた感じがしました。
「さとりのしょ」
小さいころ、ゲームが好きでした。
有名なドラクエ(ドラゴンクエスト)というゲームの中に、
「さとりのしょ」というアイテムが登場します。
これを使うと、誰でも一定のレベルに到達していれば
「けんじゃ」になることができて、能力が上がります。
今回の「英雄の書」は私にとってはまさに「さとりのしょ」でした。
悟ったというと大げさですが、
私はこの本を読んでから、かなりマインドと行動を変えています。
ゲームの「けんじゃ」もはじめはレベルが低いけれど、
成長スピードは段違いに早く、強力な戦力になります。
他人の経験から学んで、成長スピードを上げる。
本を読むってそういうことだなと改めて思いました。
「さとりのしょ」は人それぞれかもしれません。
良い本に巡り合うためにも、もっともっと、本を読んでいきたいですね。
学習記録
10/13(土)の学習記録
項目: トライアルに向けての学習(半導体)
目標: 15h 実績:14h35m
メモ: 調査(続きから):10h20m
翻訳作業:3h25m
ブログの時間の半分:50m
10/14(日)の学習計画
項目: トライアル向けての学習(半導体)
目標: 9h
メモ: 午後は用事で外出+お休み(読書や作業など)
今日は「戦略的休息」です。