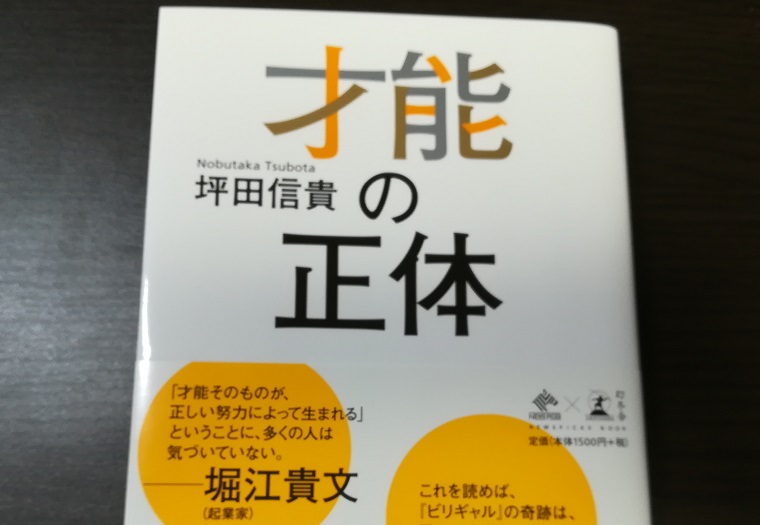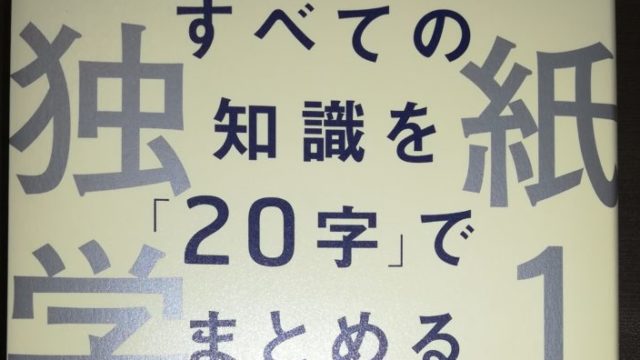「自分には才能がないから」できない。
「あの人は才能があったから」成功した。
「才能」って何かと便利な言葉ですよね。
でも、一体才能って何なんでしょう。
先日、「才能の正体」という本を読みました。
この本の趣旨は、
「才能はひとりひとりに備わっているもの」
「自分には才能があると信じて、ひたすら努力を継続すること」
「成功するかしないかはあなたのとらえ方次第」
というところにあります。
ただ、読み進めて行くうちに少し違う感想を持ちました。
それは、「いかに他人の力を使えるか」が才能を開花させるのにとても重要なのではないか、ということです。
なぜそう思ったのか、お話します。
ビリギャルと坪田さんと「才能の正体」
この本の著者、坪田信貴さんは「ビリギャル」の著者として有名な方です。
ビリギャルは、「学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話」の略です。
内容は本のタイトルのままですね。ノンフィクションです。
坪田さんはビリギャル以外にも多くの生徒さんを指導したり、「普通に社会で生きるにはしんどそうな人」ばかりを社員にした会社を成功させたりなど、ひとりひとりの才能を活かすプロです。
本の中でも出てくるのですが、「ビリギャル」が世に広まってから、
「ビリギャルはもともと才能があったんだ」、
「地頭がよかったんだ」という声が多く聞こえたそうです。
確かにそうかもしれません。
全く飲み込みが悪い生徒さんだったら、どんなにやる気があって努力を継続していてもここまでの結果にはならなかったのかもしれません。
ただ、この「ビリギャル」のいきさつを読んで私が思ったのは、
「坪田さんがいなければ、もしくは坪田さん以外の講師の指導のもとで同じ結果がでたのだろうか」
ということです。
正しい勉強方法を教え、フィードバックを繰り返し、マインドの面でもサポートする。
本来「ビリギャル」を読んでからもの申すべきでしょうけども、この本からも、どれだけ坪田さんがメンターとして重要な役割を発揮したのかがわかります。
と同時に、もちろんビリギャル(さやかちゃんといいます)が坪田さんを信頼してコツコツと努力を積み重ねたことが大きいでしょう。
ですので、さやかちゃんの成功は「しかるべき他人に教えを乞い、素直にアドバイスに従ってコツコツ努力した」からだと感じました。
もし今メンターから教えを受けられる環境にいるのであれば、さやかちゃんと同じように、メンターと自分を信用してアドバイス通りに素直に努力を続けることが、才能を伸ばして成功に近づく一番の方法なのではないかと思います。
他人を完コピすることと「術」を体得すること
そうはいっても、「この人を信じてついて行く」と思える人にはなかなか出会えないでしょう。
もし出会えたとしても、指導を受けられるかどうかはまた別の話です。
そんな時は、「お手本にしたい人」を完コピしましょう。
本では、できれば動画に撮るなどして「できる人」の一挙一動を観察し、まねることをすすめています。
できる人が何をどうやってやっているのかをまずは学んで、それから行動を完コピすることが成功の近道であると書かれています。
これは何度も「お手本」の動作を繰り返すことで、自分の既存の枠組みを取っ払って「お手本」にすり替えてしまう効果を狙ったものだと思います。
本ではさらに、動画にすると「お手本との違い」に意識が向きやすくなって、その人の行動の特異なポイントに目が行きやすくなると書かれています(「才能の正体」p.104) 。
これについて本では明確に書かれていないのですが、「その人の行動の特異なポイント」がまさに「コア」というか「その人の考え方のエッセンスが詰まったポイント」なんじゃないかと思います。
本の別のページには「技」と「術」の話が出てくるのですが、これに関係しているように感じました。
「技」とは柔道でいえば「背負い投げ」などの個別のやり方です。
それに対して「術」とは「相手が崩れた瞬間を作って狙う」などの、他の武道などにも応用できる「コツ」です。
この「術」を体得すれば、当然個別の技の上達は早いでしょう。
武道でなくても、勉強でも、仕事でも、この「術」は存在します。
「できる人」を完コピして気づいた「できる人」の特異点というのは、この「術」そのものか「術」に気づくきっかけを与えてくれるものなのではないか、だからこそ「完コピ」が有効なのではないか、と思いました。
本から「できる人」を完コピする
よし、「できる人」をまねればいいんだな。
動画を撮るのがおすすめね、わかった。
と思っても、やっぱり身近に完コピしたい「できる人」がいない場合にはどうしましょうか。
そんな時は、本から著者の行動を完コピしましょう。
最近見たyoutube動画でとても参考になるものがあったので、紹介します。
超絶お勧めの読書法(経営コンサルタント島倉大輔公式チャンネル)
この動画の中で、同じ著者の本を何冊も読んで、その著者の思考のフレームワークを抜き取るという話が出てきます(4分50秒あたりからです)。
同じ著者の本を何冊か読んだ経験がある方はわかると思いますが、結構同じ話、でてきますよね。
またきた、ほらきた。と思うんですけど、そこがやはり著者の「コア」になっている部分なんですね。
動画の中で、島倉さんはその部分が著者のポリシーや考え方が反映されているところで、思考のフレームワークともいえる場所だと話されています。
そして、優れた著者の本であれば、そのフレームワークは他の本を読む時にも応用できると言われています。
これも、「術」の一つですよね。
この動画には、その他にもすぐに取り入れたい読書術のヒントがいろいろ詰まってます。
10分程度の動画ですので、ぜひご覧になってみてください。
おわりに
「才能の正体」を読んで、「いかに他人の力を使えるか」が才能を開花させるのに大切だと気づいた、というお話をしました。
「他人の力をうまく使って成功する」ために大切なことは次の2点です。
- 素直にアドバイスを受け入れる
- できる他人をまねる・術を盗む
もちろん、次のようなマインドセットは大前提になります。
- コツコツと努力を継続することをいとわない
- 伸び悩む時期が来ることを受け入れる
- 自分はできると信じる
今日お話したことは、この本の本質とは少しずれています。
本の中では正しいフィードバックのかけ方など、何人もの生徒さんを指導してきた著者ならではの「能力を高めて、自分の才能に気づくためのヒント」が詰まっています。
特に、「私には才能なんてないし、ちょっとさすがに手遅れだし」と思っている方におすすめです。