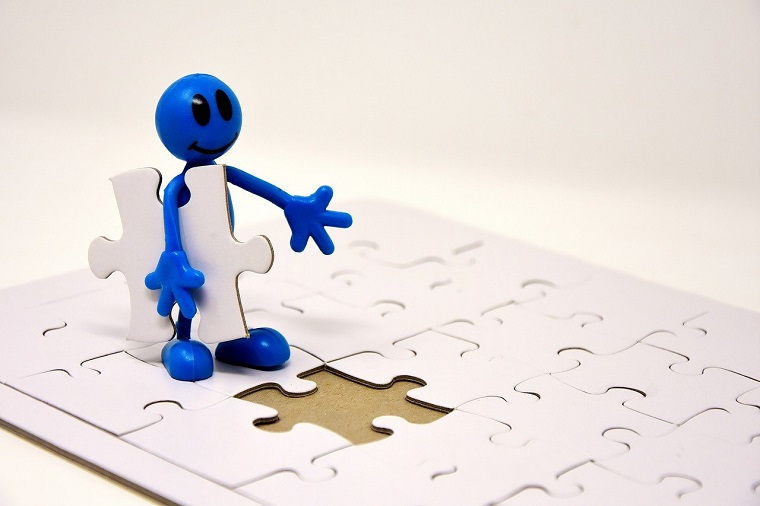学習内容
- 対訳学習(3Dプリンタを使用した製剤方法)自力翻訳→公開訳・AI翻訳と比較
- 読書「才能に頼らない文章術」「漫画 君たちはどう生きるか」
対訳学習の進捗:自分で決めた納期は死守する
先週に引き続き、対訳学習メインで進めています。
調査から「納品」までスケジュールを決めて実ジョブのシミュレーションとみなして取り組んでいます。
実は先週、お正月からのもやもやした気持ちを引きずっていたため、1~2日ほどかなり翻訳作業がスローペースになっていました(もやもやは解消しました)。
そのせいで、当初無理のないスケジュールだったもの(約7500ワードで1週間)がキツキツのスケジュールになり、2日ほど「残業」してました。
翌日遅く起きたら意味はないんですが、それでも「納期」は死守します。やはり、どうしても学習中は実ジョブの緊張感がなくなってしまうので、これは自分との約束としてこれからも守ります。
今は訳出を終えて、公開訳とAI翻訳(一部機械翻訳含む)と比較する作業をしています。
現状ではやはり係り受けが一番の問題です(詳細は別途来週まとめる予定です)。
AI翻訳とも同時に比較していますがこちらもいろんな気づきがあります。中には、自分の訳、公開訳を差し置いて「ベスト」な訳を出してくることもありました(表現的になるほど、うまいなと思ったものがあったのです)。
この素材をもう少し味わってから、類似特許(公開訳のないもの)についてもサンプルとして訳出しておこうと思います。
習慣が身につく瞬間
今週、2時起きに起床時間を固定すること、毎朝散歩すること(日中買い物にいく日以外)の習慣化に取り組みました。
2時起きは「残業」のせいで達成できなかった日がありますが、散歩は小雨決行で続けています。
恐らく、これからも続けていけると思っています。まだ1週間くらいしか経っていませんが。
というのも、すでに2時起きで調子がいい、散歩も気持ちいい、という感覚が得られているからです。
ここまで来れば、その気持ちいい状況を脳が欲するので自然と継続できます。
次は食生活の改善ですね。1日3食に戻すつもりはないですが、2食+栄養のあるおやつ(ゆで卵など)で考えています。
「読者目線」で文章を書く方法:才能に頼らない文章術
管理人さんから頂いた書籍のうち、「才能に頼らない文章術」「漫画 君たちはどう生きるか」を読みました。
今日は少し、「才能に頼らない文章術」のほうのお話を。
この本を一言でいうと、「読者目線で文章を書くスキルを学ぶ本」です。
著者は編集者として長く活躍された方で、編集者としての経験から「要点が伝わりやすく、読みやすい文章」のポイントを解説されています。
文章のチェックポイントは次の3点に分けることができます。
- 文章基礎力チェック:文章の基本ルールに則っているか
- 文章表現力チェック:段落単位の表現力は十分か
- 文章構成力チェック:文章の目的が達成されているか
①の基礎力は、句読点の付け方などのルール、表記揺れに注意することなどの基本的なお作法ができているかどうかのチェックです。
この部分については、他の本でも紹介されている部分ですね。
②は、単語単位~段落単位での伝わりやすさをチェックする項目です。
専門用語を使わない(説明を加える)、段落の中で論理破綻が起きていないか、接続詞を多用していないか、などです。
③は、文章全体のチェックで、一番高度な部分です。
例えば、タイトルや見出しと内容が一致しているかどうか、文章全体のテーマが明確か、読者が興味をもって読み切れるか、などです。
実際の添削例と添削理由もついているので、文章力を上げたいと思っている方は読んで損がない本だと思います。
私はこの本を見ながら、手元にある自分の受講感想(来週提出します)をブラッシュアップしていました。
①の文章基礎力の部分でいえば、自分の癖としても自覚している読点が多いこと、一文が長いことを特にチェックしました。
②の文章表現力の部分では、語尾が単調(でした、でした、が続く)、接続詞が多い(他の言葉に言いかえてみる)などですね。
そして最後の③が一番重要な部分なのですが、伝えたいことが果たして伝わるのかどうか、読み手がストレスを感じずに読み切れるか、を特に念頭に置いて見直しました。
ただ、これはとても難しいです。やはり「伝えたいこと」が全面に出過ぎていてかえって伝わらないのでは、という感じが拭えません。
とはいえ、いつまでもこねくり回していても仕方がないので、「これが今のベスト」というところで提出します。
ゴールテープが見えてきた
早いもので受講丸2年が近づいてきました。
実際の受講開始日(ID利用可能日)は1/22なんですが、個人的理由から来週のとある1日を「スタート」と「ゴール」の日としています。
来週は少し作業をしたいのと、1日お休みするのと、外出予定があるのとで学習に使える時間が少し制限されます。
最後まで気を抜かずに、次の1週間も駆け抜けます。
ゴール後ももちろん続くわけなので、むしろスタートダッシュですね。頑張ります。