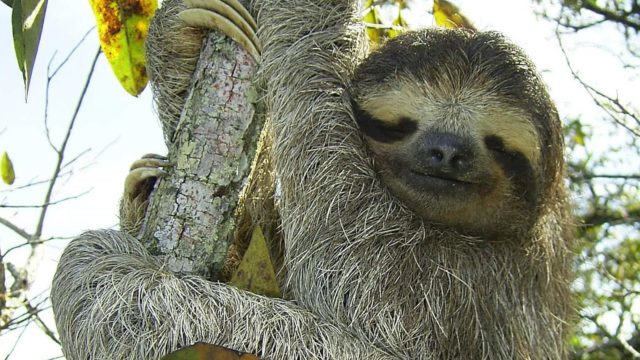1/24 ビデオ視聴の気づき
3401_同じミスを繰り返さないために、にてアドバイス頂きありがとうございました。
このビデオで、
・学習に対する姿勢(受け身である)
・失敗から学ぶ姿勢
に問題があることがわかりました。
学習に対する姿勢(受け身である)
ビデオは、昨日の記事(徐放性製剤の背景技術部分:訳して公開訳と比較する)についてのものでした。
この記事は、先日の管理人さんとのスカイプの中で「自分の訳をアップすること。悪い所があればツッコむから」という話があり、それをそのまま実行した形です。
「アップしろ」と言われたから(アップしたくないけど)アップした、という受け身な態度だったため、本当の目的(ミスを洗い出し再発防止する)を忘れていました。
失敗から学ぶ姿勢
係り受けの問題が深刻だ、ということは去年の11月頃に不合格トライアルの分析をした頃から認識していました。
その時に、「英語力の問題」とか「翻訳量が足りない」とか「読解力の問題」とかいろんな理由を付けたのですが、根本的な理由を探せておらず、またこれらの想定された「理由」を解消するために行動したわけでもありませんでした(自力翻訳で「翻訳量が足りない」を解消する方向に向かった以外は)。
つまり、ほとんど何も対策をしていませんでした。
この対策をしない限り、トライアルにも合格しないし、合格して実ジョブが来ても切られてしまうというのはもちろんわかります。
ですが、漠然と「勉強を続けていけば解決の糸口がつかめるのでは」と思って直視していませんでした。
ブログにもトライアルの振り返りをした、と書きました(実際に一文一文見直して振り返りはしました)が、その振り返りの「レベル」はこの程度でした。
もちろんミスの原因と対策を考えました。
ですが、「なぜ内容は理解できているはずなのに間違えてしまうのだろう」ということから抜け出せませんでした。
ですので当時、内容理解より文法理解力の欠如や注意力散漫なのが原因ではと思っていました。
当時すべきことは、ぎりぎりまで自分で「係り受け間違いの理由」を考え、どうしてもわからなければ、管理人さんにトライアルと類似の文を使って自分のミスを説明し、指示を仰ぐということでした。
バケツの穴が空いているのがわかっているのに、「いつか穴は塞がるだろう」と思って補修をせずに水をくみ続けている状態でした。
ですから、2年間で結果が出なかったのは必然です。
気づくのがあまりに遅すぎました。
今すべきことは、問題に真摯に向き合って、ひとつずつ潰していくことだけです。
今回の係り受けミスについて
ビデオに取り上げて頂いたミスについて、「何がミスの原因だったのか、今後どうすべきなのか」を考えました。
The present invention relates to sustained-release formulations and dosage forms of ruxolitinib, or a pharmaceutically acceptable salt thereof, which are useful in the treatment of Janus kinase-associated diseases such as myeloproliferative disorders.
(自分)本発明は、骨髄増殖性疾患等のヤヌスキナーゼ関連疾患の治療に有用である徐放性製剤及びルキソリチニブ又はこれらの製薬上許容できる塩の投与形態に関する。
(公開訳)本発明は、骨髄増殖性疾患などのヤヌスキナーゼ関連疾患の治療に有用である、ルキソリチニブまたはその薬学的に許容される塩の徐放性製剤および投薬形態に関する。
ビデオの中では、DDSに飛びつく前に薬剤や投与形態について勉強していないから「formulations and dosage forms」がチャンクで見えない、勉強していたら間違いようがない、というお話でした。
ビデオ内で「まずはこれで勉強すべきでは?」と出された資料についてはこの翻訳の前に(DDS関連の日本語明細書を読む前に)全て目を通していました。
DDSを用いた薬物投与の最適化
http://www.phs.osaka-u.ac.jp/homepage/yaku/sotugo/pdf/h18_07_1.pdf
【DDSの現状と展開】第1回 「DDSとは何か?」
https://www.yakuji.co.jp/entry8822.html
薬の投与法
https://www.nanotechss.co.jp/ikiikikurabu/kenkoujouhou/kusurinotouyohou1.html
薬の投与法については、だいぶ前に読んでおり、これまでも何度か参考にしていました。
これまでの学習法としても、明細書を読む前にこれらのまとまっているページを読んで、ノートにしたり知子の情報に入れたりマインドマップにしたり、という学習をしてきました。
また、その過程で「当初疑問だったけど解決できたこと」「なるほどと思ったこと」を都度ブログ記事にしてきました。
日本語の明細書を読んでいても「全く読めない、手強い」と思うことはなく、いくつか初めて出てきた言葉を調べながら読み進められたので、私はこれまで自分の学習法がものすごく間違っているとは思っていませんでした(明細書を読む量、翻訳する量が足りないという問題はありました。内容を理解するアプローチで、という意味です)。
ただ、「まとまり」「つながり」などを意識して勉強する、ということができていなかったのではないかと思います。
今回の例でいうと、薬の種類、投与形態の種類については知っていました。もちろんそれらが密接に関連しているということもわかります。
ですが、学習しているときに「薬の種類と投与形態は関連しているな」と思いながら読んだり、どの薬剤がどの投与形態に適しているのか、ということを意識して読んだりということはしていませんでした。
ただ、そこに書いてあることが理解できるか・できないかという観点で読み、理解できればOKとしているような読み方をしています。
例えば、下記の資料のp.7を例に挙げます。
製剤化が困難と予想される特性
1. 膜透過性が悪く、消化管からの吸収性が低く、絶対吸収効率が悪い。
2. 消化管から吸収されるが、初回通過代謝を受けやすく、絶対吸収
効率が悪い。
2. 化学的安定性が悪く、保存時の安定性の確保に困難が予想される。
4. 溶解度が低く、十分な吸収性を確保できない。
5. 消化管内で分解を受けやすい。
6. 投与量が多くなり、製造性が劣悪になることが予想される。
学習するときに、これらがどういうことかわからなければ調べて、自分の言葉に置き換えて説明できる程度には理解します。
ただ、例えば上記1.に当てはまる薬剤の代表例は何だろうか。この問題を解決するためにどういう手段があるだろうか。どんな特許が出ているだろうか、というところまで踏み込んで調べることは少ないです。
「あまり深掘りしすぎて時間をロスしないようにしないと」というのは名目上の理由で、実際はやはり「時間もかかり面倒」という理由から、このような自分で発展させて考えるという訓練を怠っていました。
こういう学習上の怠慢の積み重ねが「係り受けミス」につながっているのか、と思ったのですが実は自分の中ではまだしっくりきていない部分があります。
いずれにせよ、日本語、英語、そして自分の訳文。すべて「眺める」ような読み方をしていてじっくり読めていません。
明日からは、直近でやっていた対訳学習の係り受けミスの原因を再度分析し、再発防止策を考えることからはじめます。
そこで対策が見えない限り、次の対訳学習に進んでも意味はないでしょうから。
気づきは都度ブログにアップします。
今日のビデオ内での下記コメントについて。
「だから今の状態(トライアル合格しても繁忙期に仕事が来ない)なんですよ。へこんだ?へこむように言っているけど」
これについての答えは、
「へこみません。すでにこれ以上へこむ余地がない状態なので」 です。
落ちるところまで落ちたと思うので、ここから感情を捨て、「勉強するマシーン」になります。