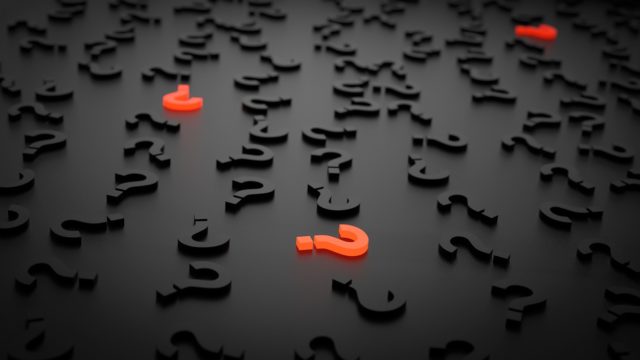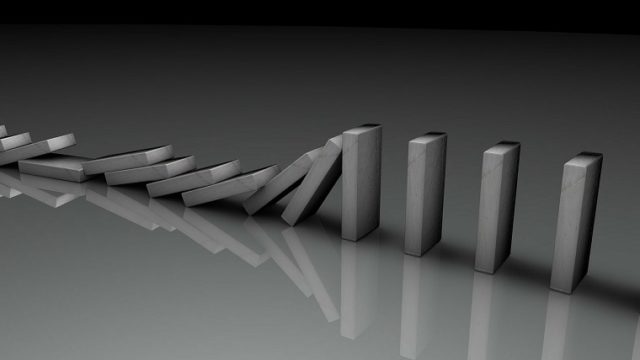2/4 学習内容
- 過去のトライアルを題材にした学習(内容理解)
- ビデオセミナー3416号(失敗の研究)視聴、まとめ
- ミス対策(詳細は後述)
- セミナー(ライフサイエンスイノベーション)参加準備(講演者の方の情報やざっくりとした業界の方向性、現状などの記事を読み理解を深める)
- 新ツールのインストール、既存ツールの使い方に慣れる
風邪をひいてしまい本調子ではないので、予定していた明細書を2件読むこと、翻訳に入ること、過去のミスをブログにアップすることはできていません。代わりに今できることをしました。
ビデオセミナー3416号(失敗の研究)にてアドバイス頂き、ありがとうございました。
自分自身と、ミスという事象とを切り離して考えられるようになりつつあるので、ビデオで指摘されたからといって凹むことはありません。
むしろ、貴重な成長のきっかけです(もちろん、自分でミス対策をきっちり考えるのが前提ですが。何でもアップすればいいとは思っていませんし、できるだけ「めんどくさいやつ」をアップしています)。
今日はミス対策として、ビデオ内のアドバイスに基づいて下記のことを実行しました。
- 知子の情報に入れている個別のミスの索引をエクセルに落とし込み、ミスパターンの分析
- ミス対応策について検索し、自分にどのように当てはめるか考える
- 過去のミスを張り出す(バイアルの写真や炭素番号を間違えたノートのコピーなどもアイコンとして張り出しています)
- 翻訳手順(チェック含む)を細分化し、見える所に張り出す
今日はすみません。
体力がないのでかなり端折って書きます(また後日書くかもしれません)。
ミス防止については複数サイトを見ましたが、こちらのサイトが網羅されていてわかりやすかったです。
https://www.consultsourcing.jp/category/miss_prevention
上記のサイトではなかったかもしれませんが、複数のサイトに、ミス防止策として「やることをできるだけ細分化して、それをチェックしながら進める」と書いてありました。
これにならい、1文1文の翻訳工程を16個の作業に落とし込みました(ものすごく細かい作業も含んでいます)。
まどろっこしいかもしれませんがこれに沿ってやって習慣化することで、どこでミスが生じやすいのか、どこを対策すればよいのかがわかるのではと思ったからです。
それとは別に、私のミス(特に、思い込み系)にはやはり「ざっくり枠組みを捉える、例える」ということが有効だろうなと感じています。
今日見ていたミス防止の方法にもあったのですが、ミスの多い人の特徴に「細かな所ばかりに目が行ってしまい知らぬ間に「目的から外れる」仕事をしてしまう」というものがありました。
これ、かなり当てはまっている自覚があります。
翻訳するには支障がない細かな情報と、理解の前提となる大枠の情報を同じ重要度で見てしまっていることがあります。
そもそも見ている木が違うのに、「この葉脈の走行は何かおかしい」とじっと見ているような感じです。
これを防ぐには、やはり管理人さんがおっしゃるように単純にして図解化したり、6歳児に例えるように説明してみる、ということが有効だと思います。
そこに残っている情報が、理解の前提となる大枠の情報、ということになると思うので。
なので、
- ミスは記録する。新鮮なうちに自分で吟味してから俎上(処刑台?)に上げる
- 翻訳とチェックのプロセスを一文一文丁寧に、貼りだした手順に沿って行う
- 図解したり例えをつかって説明して、大枠で必要な情報を捉える習慣を付ける
これらを実行していきます。