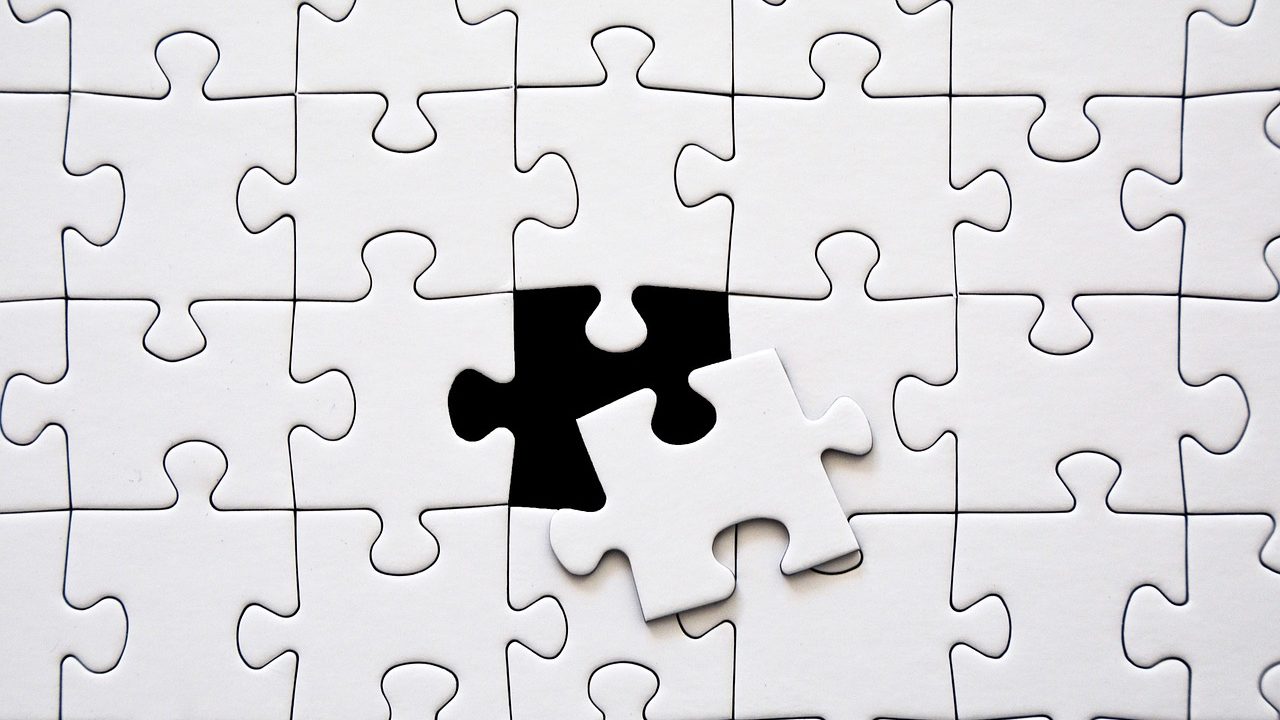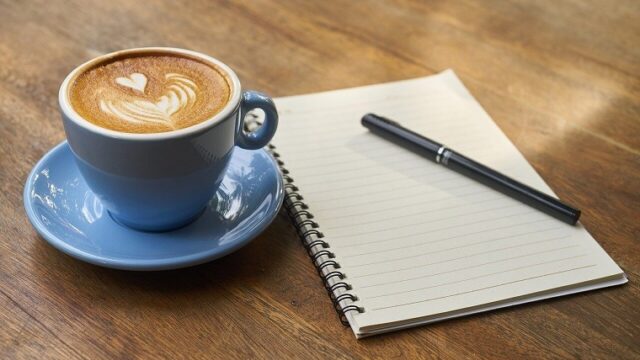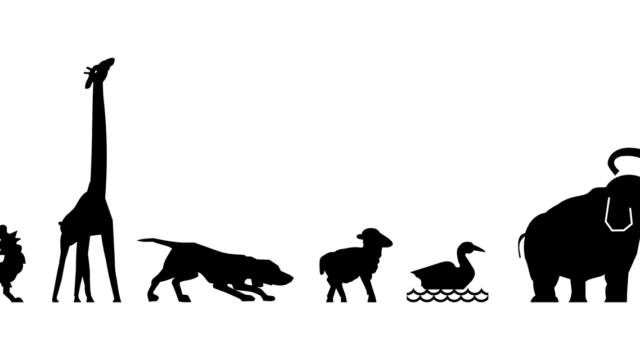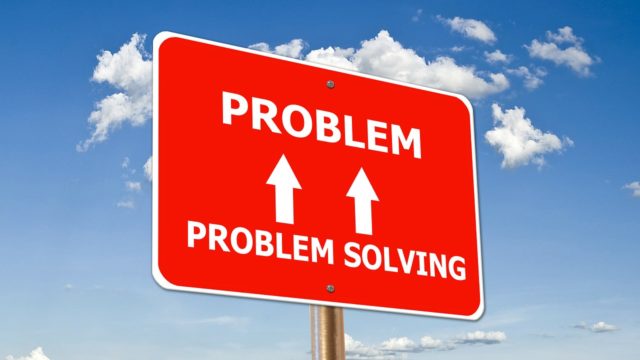週末のまとめに書こうと思っていましたが、今朝のビデオ(3507_受講生ブログへのコメント)で先週のログにコメントを頂いたので単独で書きます。
「振り返り」といいつつ一文ずつ再度分析する、というところまではやっていないので(仮)です。
トライアル振り返り
今週、トライアル解答を提出しました。
結果はまだですが、自分では99%、不合格だと思っています。
なぜかというと、請求項部分で自分でも納得がいかないまま提出してしまった箇所があるからです。
まず、提出時に最低「これで大丈夫」と自分で思えないレベルであれば合格することはないでしょう(これは、過去のトライアルでも実感としてあります)。
1%の可能性は、「他の部分はそこそこできているから1度やらせてから最終判断しよう、人手も足りてないし」というミラクルがあるかも・・・という淡すぎる期待なので(請求項でのミスはやはり致命的だと思うので)、この可能性は考慮せずに落ちたものとして学習を進めています。
今回のトライアルは、非常に実践的なトライアルでした。
「実践的」というのは、トライアルのために問題を作った(または選んだ)というより、少し難しめの実ジョブをまるごと投げられて、訳す場所だけ指定がある、といった印象で、
メールのやりとりから納品まで、すべて含めて「即戦力で使えるかどうか」を判定されている、といった感覚が他社のトライアルよりも強かったからです。
内容の把握については、それほど苦労はしませんでした。
それなのになぜ請求項でつまずいたのかというと、「普通に訳すと矛盾してしまう」と感じる部分があり、それをどうさばくのが「正解」なのかが最後まで見えなかったからです。
a、theの並びで既出と初出の矛盾が起きないように、という話ではなく、内容的に矛盾してしまうのです(詳しくはもちろん書けないのですが・・・矛盾というより「違和感が残る」のほうが近いかもしれません)。
「内容を理解した」といいつつ、盛大に勘違いをしているのでは?矛盾でも何でもないのでは?と思い何度も見直すものの、そうとしか読めない。
そうであれば、あとは請求項をうまく組み立てるしかない・・・と思うものの、どこまで「手を入れて」よいのかわからない。
そもそも、請求項の「お作法」的な部分で勘違いをしているのでは、と思いいろいろ調査するも解決せず。
最終的に「形が微妙に違う(と思われる)ピースを無理矢理はめてごまかした」状態で提出しました。
提出後やったこと
今回のトライアルで引っかかった点、今理解していることなどをまとめてから、請求項の翻訳のレベルアップを図ることにしました。
上記で書いた事以外にも、同じく請求項の部分で「これはどうしたらよいのか」と悩んだ点もあったためです。
トライアル中に関連のビデオ、知子の情報に入れたものやノートなどは見直したのですが、それに加えて少しややこしそうな請求項を探し出して、英文で内容をおおよそ把握して、日本語の明細書部分を読んで請求項部分のみ訳す、ということをしていました。
3件ほどやってみて、基本的なところは問題ないことがわかりました。
あとは結局は、案件ごとの違いであったり、出願人や出願国の癖によるもの、そして内容を確実に理解できているか(各要素の関係がわかっているか)だと思います。
対策としては、各要素の関係を把握しながら読む・訳す、ことを意識しつつ量をこなすしかないと考えています。
トライアル取り組み中は、解答提出後は課題文の未翻訳部分を翻訳してもう一度課題文部分を見直そうと思っていましたが、いざ提出を終えるとどうしても見直す気がしませんでした。
今朝のビデオを視聴して、「逃げるな」という声が聞こえてきました。正式に結果が出てからのほうが冷静になるかな、と思って「後で」にしていましたが、たぶんこれは痛みから逃れるための都合のいい言い訳です。
ということで、今日からもう一度見直すことにしました(今日のところは、ざっと内容を復習して、未翻訳部分を翻訳しています。並行して、日本語の同分野の特許明細書も読んでいきます)。
今回のトライアル受験で得たこと
(トライアルまでの)学習濃度が上がったこと
今回のトライアル受験を決めたのは、およそ1ヶ月前のことです。
その当時は、翻訳ミスも多く「これじゃどう考えても受からない」と思い、当初4月からスタートとしていたトライアル受験時期を後ろ倒しに(GW明けに)していました。
ビデオで「早く、いいから、トライアル受けろ!どうなっても知らんぞ(超訳)」とアドバイスいただいてから、考え直しました。
そこから、今から合格まで持っていくためにはどうすればよいだろうか、足りないものは何だろうか、と今まで以上に真剣に考え、勉強してきました。この過程で、翻訳レベルは確実に以前より上がったと実感できました。
もちろん、目に見える結果を得るためにやってきて、それが(恐らく)実現しないのはとても悔しいです。ただ、上記の理由から挑戦は無駄ではなかったと思っています。
自分の現在のレベルを実感できたこと
まだ、「すぐ仕事が来るレベルでトライアル合格」には遠いことがわかりました(ここに書いた請求項以外でも、補強しなくてはならない項目はいくつかあります)。
ですが、「落ちるとしたらあそこで落ちるだろう」という感覚が今回持てたので、これはひとつの進歩だと思っています。
他の箇所は、もしかしたら表現の方法などで評価がマイナスになることはあるかもしれませんが、内容理解で外しているところはないはずです。
今回は「自分がチェッカーだったらどう思うか」という点で訳文をチェックするようにしていました。これまでのトライアルで、かなりこじらせた訳文を出してしまったことがあったので、その反省です。
これによって、コメントをつける・つけない、どのようにつけるか、についても以前より冷静に判断することができたと思っています。
次へ向けて
このトライアルを足がかりに学習を進めます。
この特許のコアになっている技術(というより現象)を利用しているものは多岐に渡るので、少し足を広げていろんな特許を読みながら、もう一度「ベスト」な解答を作ります。
次のトライアルはGW前に設定します。
仕事を一旦ストップしてからこれまで、「バイオメディカル分野である程度高レートで参入する」ことを目標としてやってきました。
もちろん、これが理想であることは変わりません。
ただ、現在の状況(社会情勢、そこから影響を受ける翻訳業界の状況、そして自分のレベル)から、「分野、レートにかかわらずまずは(夏までには)どこかに潜り込んでレギュラーになる」ことを目標にしていこうと思っています。
よほど特定分野の人材が足りないという状況にでもない限り、これから新人への門はますます狭くなり、門に集まる人はますます増えるのは明らかです。
このような状況の中で、まだドアが開いているうちにとにかく「滑り込む」ことが大切なのではないかと現時点では考えています。
1年前、狙いを定めて脇目も振らずに集中していたら。
1年前に「需要がある」と言われた分野も今では状況が変わっています。1つの判断の差で大きく差がつくのだということを今回改めて痛感しています。
過去の決断について今さらどうこう言っても時間の無駄にしかなりませんので、将来のために、今すべきことをやっていきます。