こんにちは。
今日は先日ご紹介したメディカルライティングの書き方の本
「こうすれば医学情報が伝わる!! わかりやすい文章の書き方ガイド」の
内容を元に、
「こうすると伝わらない!わかりにくい自分の訳文にダメ出しする」を
テーマにお送りします。
ダメ出し1:長い修飾語が後に来ていてわかりにくい
ここからは、恥を忍んで自分の実際の訳文を晒します。
全て、抗凝固薬の添付文書(こちら)からの一文です。
まずはこちらです。
ELIQUIS increases the risk of bleeding and can cause serious, potentially fatal, bleeding [see Dosage and Administration (2.1) and Adverse Reactions (6.1)].
(自分の訳文)
本剤は出血のリスクを高め、重篤な、死に至る可能性のある出血を引き起こすおそれがある[用法・用量(2.1)及び副作用(6.1)を参照のこと]。
青字部分のserious, potentially fatal をそのまま「重篤な、死に至る可能性のある出血」と訳しました。
意味はわかるのですが、少し読みづらい感じがしませんか。
こちらが公開訳です(こちらの文章を「公開訳」としています)。
(公開訳)
本剤は出血リスクを増大させ、死に至る可能性のある重篤な出血を生じるおそれがある[用法及び用量(2.2 項)、副作用(6.1 項)を参照]。
(自分の訳文)
本剤は出血のリスクを高め、重篤な、死に至る可能性のある出血を引き起こすおそれがある[用法・用量(2.1)及び副作用(6.1)を参照のこと]。
順番が違うだけですが、公開訳のほうが読みやすいと感じるはずです。
「こうすれば医学情報が伝わる!! わかりやすい文章の書き方ガイド」にも、
「日本語の作文技術」という本からの記述の引用として、
「長い修飾語ほど先に、短いほど後に」という原則を紹介しています。
ダメ出し2:主語と述語が遠い
主語と述語が遠くなってわかりにくい、というのはこれまでも自分の癖として認識していました。
ですが、まだやらかしてます。
比較すると一目瞭然です。
The safety of ELIQUIS was evaluated in the ARISTOTLE and AVERROES studies [see Clinical Studies (14)], including 11,284 patients exposed to ELIQUIS 5 mg twice daily and 602 patients exposed to ELIQUIS 2.5 mg twice daily.
(自分の訳)
本剤の安全性は、1日2回本剤5mgを投与された患者11,284例と、1日2回本剤2.5mgを投与された患者602例とを含むARISTOTLE試験及びAVERROES試験で評価された[臨床成績(14)を参照のこと]。
これは、遠いですね。
最後にたどりつく頃には、主語がなんだったか忘れているほど遠いです。
公開訳はうまくさばいています。
(公開訳)
ARISTOTLE 試験及びAVERROES 試験において本剤の安全性が評価され[臨床成績(14 項)参照]、11,284 例に本剤5 mg 1 日2 回、602 例に本剤2.5 mg 1 日2 回が投与された。
(自分の訳)
本剤の安全性は、1日2回本剤5mgを投与された患者11,284例と、1日2回本剤2.5mgを投与された患者602例とを含むARISTOTLE試験及びAVERROES試験で評価された[臨床成績(14)を参照のこと]。
本では、「何は(何が)どうであった」という形は情報の基本骨格であり、
基本骨格を持つ情報を伝えるときには
「何は(何が)」と「どうであった」を離さないこと
が大切であると書かれています。
ダメ出し3:「~においては」の多用
今回のラストは、ついつい使ってしまう「~において」「~における」などの言葉に関するものです。
The duration of ELIQUIS exposure was ≥12 months for 9375 patients and ≥24 months for 3369 patients in the two studies.
(自分の訳文)
2つの試験において、本剤の投与期間は9375例の患者においては12ヶ月以上、3369例の患者においては24ヶ月以上であった。
「おいて」がくどいですね。
他の言葉に置き換えられないでしょうか。
公開訳をみてみましょう。
(公開訳)
2試験における本剤の投与期間は、9375 例で12 ヵ月以上、3369 例で24 ヵ月以上であった。
(自分の訳文)
2つの試験において、本剤の投与期間は9375例の患者においては12ヶ月以上、3369例の患者においては24ヶ月以上であった。
公開訳はすっきりしていますね。
本では、「おいて」については次の3種類に分類され、それぞれ「で」「では」「の」「での」「に」などに置き換えることができると説明されています。
3つの「おいて」
- 場所を示す:例)今年度の当学会は東京において開催する
- 時間を示す:例)第二期においては有害事象が認められなかった
- 関係を示す:例)本剤においては良好な忍用性が認められた
(「こうすれば医学情報が伝わる!! わかりやすい文章の書き方ガイド」p.32より引用)
書き換え例です。
- 例)今年度の当学会は東京で開催する
- 例)第二期では有害事象が認められなかった
- 例)本剤の忍用性が良好であった
(同p.32-33より引用)
私と同じように、「おいて」「おける」などをついつい多用してしまいがちな方は、短い言葉に置き換えられないか立ち止まって考えてみましょう。
まとめ
今回は、下記の3つのポイントからわかりやすい文章にするヒントをご紹介しました。
ポイント1:長い修飾語ほど先に、短いほど後に置く
ポイント2:主語と述語を近づける(「何は(何が)」と「どうであった」を離さない)
ポイント3:「おいて」「おいては」を多用せず他の言葉に言い換える
今後も「わかりやすい文章」にするためのポイントをお伝えしていきます。
どうぞお楽しみに!



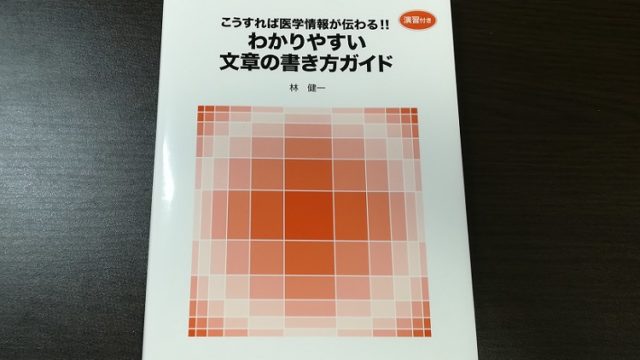



こんにちは。
実ジョブで忙しいのにコメント書いちゃっていいかな、とは思いつつ、
でも、私が正に悩んでいた点を解決してくれそうな本を紹介してくださったので、
お礼をひと言伝えたくてコメントしました。
こういう本、1冊手元にあったら心強いですね。
早速ポチりました!!
前回のログでも、「認める」ってよく見るのよ、そうなのよ~!と一人で頷いてました(笑)。
暑い日が続いていますが、頑張りましょうね!
k2challengerさん
こんにちは、コメントいつでも大歓迎ですよ!
こちらこそ、実ジョブでお忙しい中
コメントありがとうございます。
「わかりやすい文章の書き方」ならいろいろ他にもあるんですが、
医療文書に特化してるのは割と少ないのではないかなと思います。
私もまだ、全部読めていないので読み進めていきます。
ほんとに暑いですね。
バテないように、頑張りましょう!