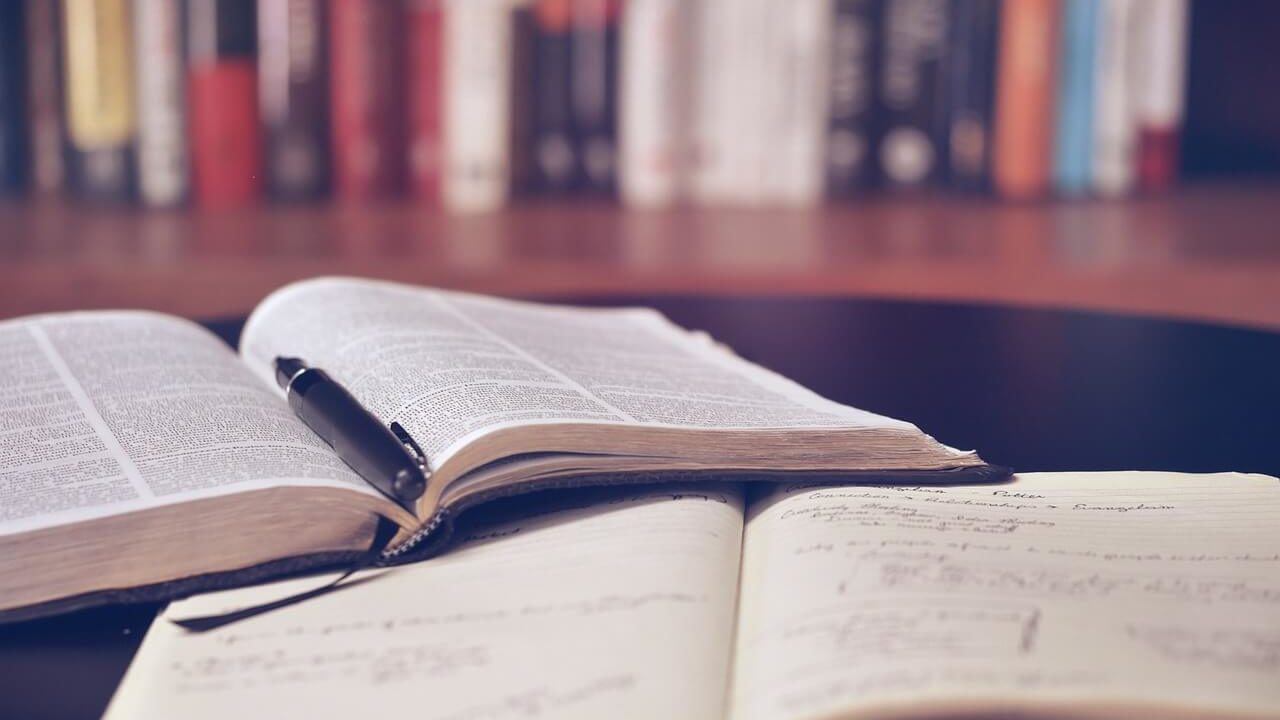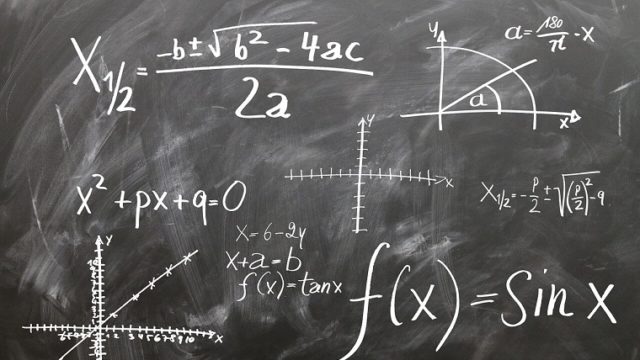波に揺られつつ
橋元の物理は波の勉強に入り、それこそノリノリでやってます。
これから「あーわからん」の波が押し寄せてくるのかもしれませんが。
今日は波に揺られつつ、月曜日に読んだ断熱膨張に関する特許明細書から気付いたことを書いておこうと思います。
断熱膨張って?
外部からの熱の出入りがない断熱の容器があります。中には気体が詰まっていて、何らかの力で膨張したとします。
この状態をものすごくざっくり説明すると、
中の気体は膨張という仕事をして、エネルギーを消費しました。
残念ながら応援(外からのエネルギーの補給)はありません。
気体が持っているエネルギーというのは熱なので、エネルギーを回復できない気体は、熱を奪われ温度が下がってしまうのです。
つまり、断熱状態で膨張させると、温度を下げることができるのです。
・・・さすがにちょっとざっくりしすぎました。
これが、エアコンなどの「冷やすメカニズム」にも使用されています。
ダイキン工業株式会社のサイトの説明はやっぱりわかりやすいですね。
概念と概念の結び付け
10件近くの明細書をざっくり読んで、気が付いたことがあります。
温度を冷やす→冷却するもの→エアコン、冷蔵庫、冷却スプレー・・・という思考しかなかったのですが、それは断熱膨張という現象の一つの側面に過ぎないということです。
明細書を見ていて、確かに冷却に関するものが多かったのですが、急激に温度を低下させ気体から液体に変化させることを利用した特許も目立ちました。
例えばですが、
- ガスクラスターを発生させる装置
- 捕集したいガスなどを凝縮して液化することで取り出しやすくする機構
などです。
ガスクラスターについては、今回は説明を省きます。
アルバック・ファイ株式会社 のサイトがわかりやすかったです。
温度と圧力が変われば物質の相が変わるというのは、岡野の化学でもさんざんやった「基礎的な概念」の一つです。
これと今回の熱の法則という「基礎的な概念」の紐づけができれば、「凝縮させることで気体を液体にして何かを取り出したりできるのでは」といった先読みができるのだろうなと思いました。
クラスターも、水素結合のところでやりましたね。上のお団子を取ったら全部だまになって引っ付いているイメージです。ここまでは知識として定着しています。
その時に、実はガスクラスターについても少し勉強していたようなのです。知子の情報にはクラスターの種類、という項目があったんですが、うーん、作った記憶がありません。
ということで、学んだ概念を自由に発展させる、というところまでは程遠いな、というのが今回よくわかりました。
クラスターについては、かなり面白そうなのでもう少し知りたいなぁと思いつつ、フックをかけっぱなし状態にして今日も波乗りに行きます。
6/12(火)の学習記録
項目: 橋元の物理(58)~(59)途中まで
目標: 6h50m 実績: 6h45m
メモ: 昨日の断熱膨張の資料のまとめ(1h)含む
6/13(水)の学習計画
項目: 橋元の物理(59)途中から
目標: 6h10m
メモ: 夜は歯医者へ(終わる終わる詐欺。でも本当にあと1、2回)