8/19~21の記録
- 実ジョブ(17~18件目)
- トライアル応募先リスト更新
- メディカルライティングセミナー参加準備
先週末から実ジョブにだいぶウエイトが偏っております。
この3日間も仕事メインで、先週から積み残していたトライアル応募先リストの更新と、メディカルライティングセミナー参加準備を合間に進めました。
ジョブは納期を前倒し前倒しで進めてかなり集中してやってきました。
胃もたれ中
先週のログにて、ミルフィーユみたいに土台(学習)と中身(ジョブ)のバランスが大事だということを書いたんですが、ここ何日かは完全に中身が飛び出て崩れてます。
今やっている案件の原文が英語と中国語のミックスで、しかもその英語部分にかなり手を焼いておりまして、少々胃もたれ気味です。
思ったんですが、実ジョブと学習のバランスはどちらかというと焼き肉の肉と野菜の関係に近いかもしれません。
肉だけでは胸やけしますし、野菜に含まれるビタミンやミネラルがタンパク質の代謝に一役買っているんで、「学習」を挟まないと実ジョブで得た経験はうまく消化できないんじゃないかなと思います。
そう思ったのは、最近の実ジョブで「全然ダメじゃないか」と思ったことがあったからでした。
置換屋、登場
前のログで、「訳語確定が遅い」という話をしました。
翻訳時にスルーしてしまって、チェックの時によくよく考えるとあれ?となってしまう。
訳語候補から瞬時に正しい方を選べない。
原文ミスかどうかの判別がつかない。
これらの「チェックに時間がかかっている」ことの根本的原因は、やはり「理解して訳していないから」というところにたどりつくなということを実感することがありました。
いきなりまた妙な例え話をします。
「打蛋」という中国語があります。
蛋は「卵」を意味します。
打蛋器という「打蛋」するための機械もあります。
さて、この「卵を打つ機械」、何のことかイメージわきますか。
正解は、泡だて器です。
「打つ」という言葉から泡だて器は想像しにくいので、割と難しかったのではないでしょうか。
例えば、「卵を打つ機械を使ってケーキを作った」という一文があればものすごく違和感ありますよね。
実は私、最近上のような文章に違和感を感じず訳してしまい、チェックの時に「なんだこれは」と気づくということをやらかしました。
チェックで気付くならいいじゃん、と思うかもしれませんが、この時の私は、「打蛋」のイメージを思い浮かべずに「置換」していたことになります。
これはダメです。
実際の文章はある画像診断装置による所見に関するものでした。
「卵を打つ」よりももう少し自然な日本語ではあったのですが、「原文のまま日本語に置き換えたら意味を正確に反映していない」言葉でした。
原文が何を表しているのか理解して訳していれば、「卵を打つ」的な訳語にはまずならなかったはずです。
なので、チェックがどうこう、見切りがどうこうの話ではなくて、単純に「わかって訳しているかそうでないか」の話です。
この基本にもう一度立ち返る必要があると感じました。
今やっている案件は診断書の翻訳なので、技術的な背景知識があるわけではありません。
ですが、どういう症状が起きているからどんな画像所見が表れて、他にもこういう所見があって、結果としてやはりある病気だと診断された、というのはある程度論理的な流れがあります。
その流れが見えているかいないかで訳文の質が大きく変わってしまうというのは、どんな翻訳案件であれ変わらないのではないかと思います。
なので、この流れを早く正確につかむことが、結局は訳語確定のスピードを上げるということにつながるのだと改めて感じました(いつも講座で言われていることですが)。
そのためには背景知識を身に着けること、図解化したり自分の言葉でまとめ直して理解しているかチェックすることですね。
納品前に、どんな案件なのか自分で説明してみる。
簡単な図を書いて理解が正しいか確認してみる。
納品後に、今回の案件で学んだ事柄について少しだけ深掘り・横展開しておく。
これを「必ずやること」としてスキームに組み込みました。
明日の予定
- 実ジョブつづき
- 打ち出しっぱなしの資料を読んでまとめる
- 分子病理検査の学習の続き
- 毒性試験の学習に入る
時間の記録
8/19 : ジョブ 13h40m

8/20: 15h20m (学習:9h10m 、ジョブ:6h10m)

8/21:11h50m (ジョブ:10h20m、学習・用語集整備のみ:1h30m)+スカイプコンサル用資料作成
*スカイプコンサル用資料は明日(8/22)朝提出します。








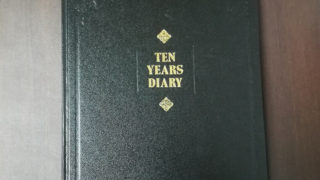

ブログ内の「卵を打つ」を見て、まさしく英語の “beat egg”が頭に浮かびました。
ミキサーや泡だて器などで、卵を泡立てる感じですね。
どちらかが、真似をしたのか。
それとも、たまたま両言語ともに同じ使い方になったのか。
こうやっていろんな言語を比較してみるのも楽しいなぁ、やっぱり言葉は面白い!と、改めて思いました。
これからもasaさんのブログ、楽しみにしています!
moncanaさん
コメントありがとうございます!
そうか、英語も一緒なんですね。
今まで「泡立て器」という英語を使ったことがなかったです(たぶん)。
同じ発想なんでしょうねー。
whipperとは言わないのかなと思って画像検索してみたら、
ホイップクリームを作る専門のような、egg beatとは違う形のものが出てきました。
中国語でも、「攪蛋器」(卵を攪拌する)というそのものズバリな言い方もあります
(これは使っている地方の違いが大きいです)。
ほんと、言葉って面白いですよね。
まだまだ暑い日が続きますが、鬼実ジョブモード、頑張ってくださいね!