こんにちは、asaです。
今日はトライアルにまつわる、「わたし」のちょっとしたお話をしてみようかと思います。
これからトライアルを受ける、あるいは解答を作成して提出するばかりだという方には参考になることもありますので是非ご覧ください。
*この物語はフィクションです。
Contents
はじまり
今からおよそ1ヶ月前のある日・・・。
そんなこんなで、正体不明のかみさまとの「トライアル課題文提出直前の見直し」が始まったのでした。
その1.「ガイドラインに載ってた」
ガイドライン、学会・協会などのウェブサイトを参考にすることは多いですよね。
そのまま使える、使うべきことも多いのですが、その場合でも「目の前の原文に対してそのまま適用してよいのかどうか」を自分で判断して用いる必要があります。
「○○に書いてあったから」だけでは訳語確定の理由にはなりません。
「権威のある情報」だからといってそのまま鵜呑みにしない。最終判断を下すのは自分であることを忘れてはならない
その2.つながっていない接続詞
接続詞はウィンカーのようなものだと、以前読んだ『文章が劇的にウマくなる「接続詞」』という本に書いてありました。
適切なタイミングでウィンカーが出され、出したウィンカー通りに車が進んでいけば、後ろを行く車はストレスを感じることなく進むことができます。
ウィンカーが左に出ているのに直進したりしたら、怖くて後ろは走れないですよね。
文章上でそういうことが起こると、読み手は理解できません。
例えば次の文は出したウィンカーと進む方向が違っていると感じると思います。
「私は映画を見るのが好きではありません。なので、ラーメンを食べます」
もう一度訳文を初めから読み直したときに、上記の文章を読んだときのような違和感がありました。
一文一文をじっくり見ていると、前後の文のつながりをおろそかにしてしまうことがあります。
文章全体の意味を把握して、前後のつながりを確認しつつ翻訳することが大前提ですが、チェックの項目に「接続詞を確認する」を入れて念のためにチェックを掛けてもいいかもしれません。
接続詞が適切かどうか確認すべし(通して読んで引っかかりがないか、接続詞だけピックアップして前後がつながっているか確認する、など)
その3. 「よかれと思って」はだいたいよくない
トライアルでコメントを付けるか否か、迷うことは多いですよね。
明らかな原文ミスなど、確実な根拠がある時以外には付けない方が無難だと思います。
とはいえ、「ここにコメントを付けるかどうかを見ているのではないか」という箇所があると、付けなくてはと思ってしまいます(少なくとも、私はそうです)。
ただ、仮にコメントが的外れであった場合、大きな減点になるはずです(あくまで推測ですし、ケースバイケースだとは思いますが)。
コメントを付ける時は、よくよく冷静になって、本当にそのコメントが必要なのか考えるべきでしょう。
コメントは確実に必要な箇所にだけ付けるべし。チェック時にそれは本当に相手にとって必要な情報か、再度確認しよう
その4. 違和感を感じたところには必ず何かがある
「直感は往々にして正しい」と言いますが、翻訳にもそれは当てはまるのではないかと感じることがあります。
それは恐らく、集中して翻訳していてその文章の「世界」に入っていた時に、自然と「これだ」というものが見えてくるからだと思います。
少し時間をおいて見直しをした時に、他の訳語候補が出てきてそれが関連する学会の用語集に出ていたために「この意味で使っているのか」と考え直し、さらに使われ方を調べてその訳語で合っているだろうと(かなり強引に)確定し、さらにコメントまでご丁寧につけていました。
その1「権威にすがる」+その3「不要なコメント」との合わせ技でこれが恐らく、致命的だったと思います。
当初の候補訳も記録しておき、迷った時には文章の意味から論理的にどちらがより適切か(あるいは、どちらも適切ではないのか)を判断する必要がありますね。
直感は往々にして正しいので、訳語候補は残しておくこと。違和感を感じた部分にはとことん向き合うこと
その5. なじみのある単語こそ慎重に
deviceは文脈によって「素子」だったり「デバイス」だったり「機器」だったりしますよね。
同じように、文脈によって使い分けるべき単語がありました。
頂く案件の中にも頻出の単語で、ここでは違う意味なので違う訳語をあてるべきですが、そのままいつも通りに訳出していました。
なじみのある単語こそ慎重に。複数意味のある単語の場合、事前にJustRight!などの校正ソフトやマクロなどに登録しておくのもありでしょう。
まとめ:トライアル提出前に確認したいたったひとつのこと
ここまでの「わたし」の経験から得た教訓5つをまとめます。
- 「権威のある情報」だからといってそのまま鵜呑みにしない
- 接続詞が適切かどうか確認する
- 不必要なコメントがないか確認する
- 違和感を感じた部分にはとことん向き合う
- なじみのある単語こそ慎重に扱う
これらをチェックすることで、合格に近づく可能性はあります。
ですが、実はこれらは不合格の根本的な理由ではなく、ただチェックするだけでは確実な合格には結びつきません。
それでは、不合格の根本的な理由とは一体何なのでしょうか。
それは、「課題文が完全に理解できていない」ことです。
理解できていれば、上記のすべての間違いは起こりえないでしょうから。
理解していない部分を「理解できていない」と認識せずに想像で埋め合わせたり「なかったこと」にしてしまうから、文章のつながりが見えない、単語ベースの誤りに気がつかないといったことが起こります。
今回、複数の課題文(さらに、複数社のトライアル)を並行していて、少し行き詰まりを感じたら他の課題に移ってしまっていました。
結果としてひとつの課題に深く集中することなく、理解が浅いまま「わかった」つもりになっていました。
複数の課題文に同時に取り組むこと自体が悪いことではないと考えます。
違う課題文を「逃げ場」にして、ひとつひとつの課題文の理解度を高めずに、そして自分の理解度を確認せずに訳し、チェックをしていたことが不合格の理由であると考えています。
「自分はこのトライアル課題文を本当に理解したか」をあらゆる角度からチェックすること、それが「トライアル解答提出前に確認すべきこと」です。
おわりに
*この物語はフィクションです。
Just Right!6 Proについては、こちらの記事で詳しく説明しています。


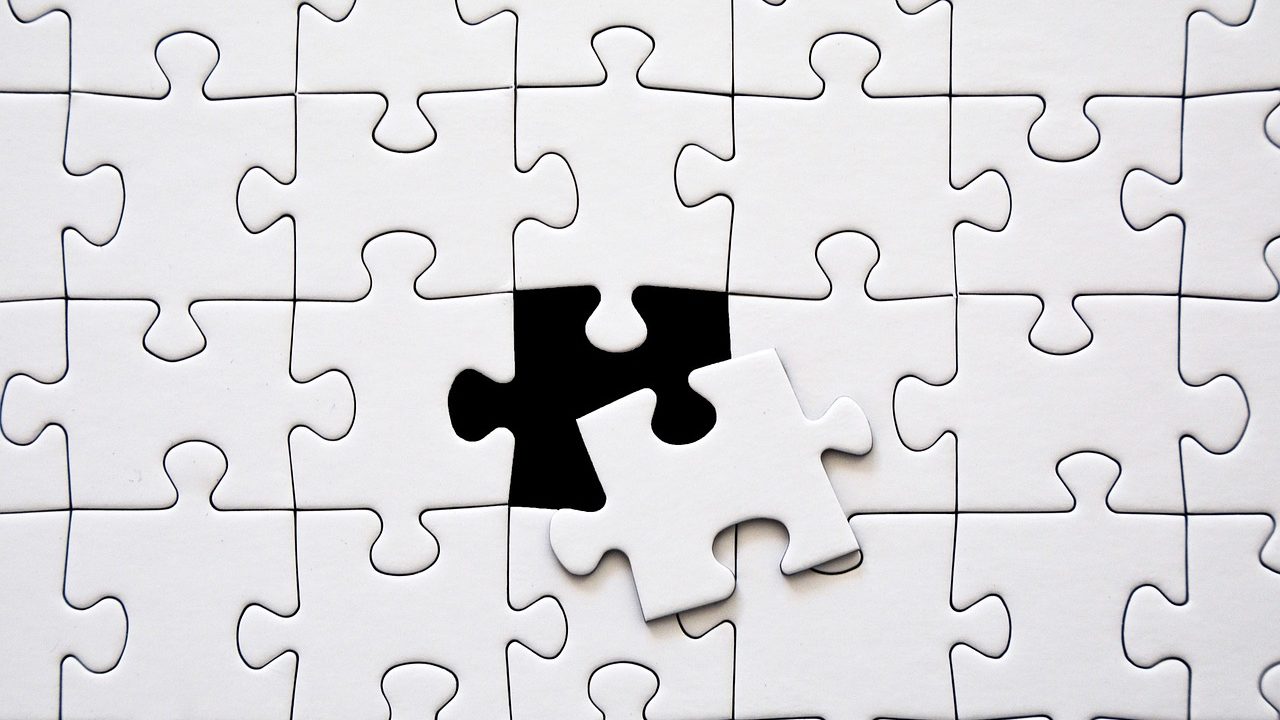

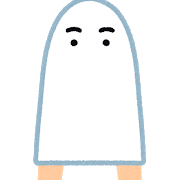
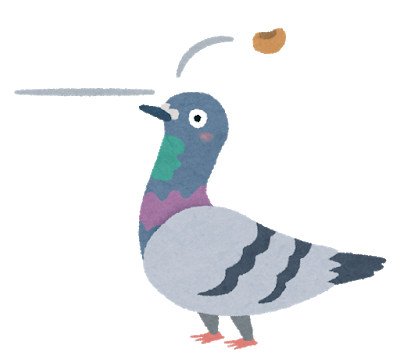
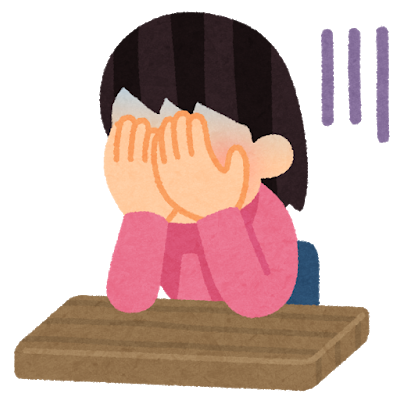









asaさん
こんにちは。
この記事、ほんっと大好きです!
トライアルが一区切りついたところでしたが(提出はこれから)、このタイミングで記事を読むことができてよかったです。
コメントの付け方、悩みますよね。
「(相手が)このコメントを見た後にすべき行動が見えない」というような内容だったり、「絶対に必要な情報」ではなかったり。冷静に見てみるとそんなコメントを書いていたことに、後から気づいてゾッとするという経験、私にもあります(涙)
とても参考になりました。
登場キャラクターも会話のやり取りもとてもかわいくて、中身は意味のある記事。asaさん、さすがです!
ありがとうございました!
Kaoさん、こんにちは。
コメントありがとうございます!
気に入っていただけてよかったです!
そのまま「反省文」として書いてたら
沈みすぎてブラジルまでたどりつきそうな勢いだったので(笑)
トライアルほぼ完了、お疲れ様でした。
Kaoさんには本当のトライアルの神様が微笑むはずです。
最後の最後、提出まで気を抜かずに頑張ってくださいね!