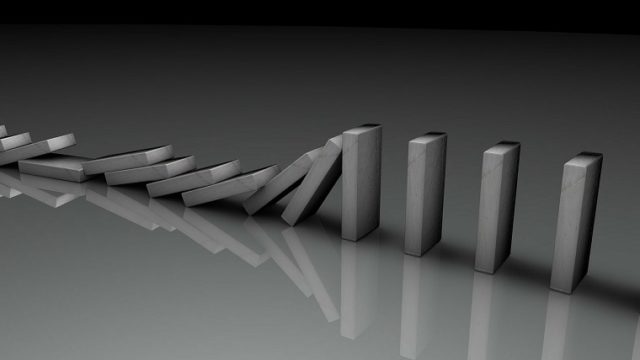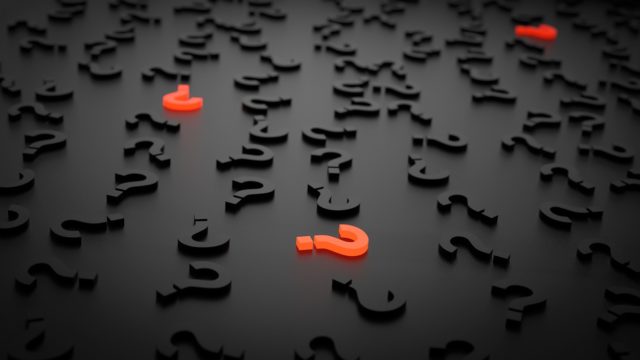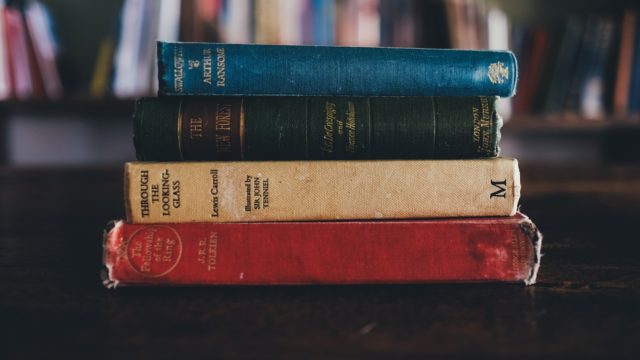1/30 学習内容
- ビデオセミナー3409号(トップレベルの訳語確定術)視聴、まとめ
- 凍結乾燥について学習(メーカーHPなどで学習、用途を特許検索しつつマインドマップにまとめる、関連特許を5件読む)
- 剤形と投与形態について再度まとめる
- 対訳学習 進捗:翻訳1242w(うち 自力翻訳132w、チェッカーモードで収集1106w)
*翻訳済計7013w/全15629w、登録した用語:132w
ビデオセミナーの気づき
ビデオセミナー3409号(トップレベルの訳語確定術)にて、昨日の記事にフィードバック頂きありがとうございました。
改善すべきところがわかりました。
できていなかったところをまとめます。
- 「reconstitution」と「再溶解」のそれぞれの意味の範囲を正しく捉えられていなかった。
- 「正解の訳」を検索して探している状態。自分で訳語を確定するというマインド、そのアプローチ、どちらもできていない。
- 言葉を何も考えずに使っている。ミセルを溶解する時に使用する溶媒は水とは限らない。疎水性ミセルや両親媒性のミセルであれば有機溶媒に溶解するものもある。
実は、自分の「ダメさ」を一番実感したのは上記と別のところにありました。
それは、引用したイートモの例文にバイアルが出てきて、ビデオ内でバイアルに注射器を刺して吸い上げる画像が出ていたときに、「あ、そういうことだったのか」と思ったことです。
というのも、バイアルについて「よく凍結乾燥粉末が入っている小さな容器」という認識しかしておらず、どういうしくみになっているのか、どうやって調製するのかを意識したことがなかったからです。
以前の誤訳(formulations and dosage formsの話)で「剤形と投与形態という基本的なところがわかっていないのでは」とご指摘いただいたことがありました。
その時、「いやいや、それはわかってます」と当初思っていました。
・・・が、やっぱりわかってなかった、ということが今回上記のバイアルの1件でよくわかりました。
もう一度剤形、投与形態、特徴、それぞれの剤形で見られる明細書の背景技術部分を紐付けてノートにまとめています。
このあたりの紐付けができているかいないかで、訳語確定の精度が変わってくるということが今回、よくわかりました。
「わかっている」と思っても一旦立ち止まって、マインドマップなどを利用して概念をまとめていきます。
凍結乾燥について
同じく、凍結乾燥についても「真空状態で水分を蒸発させてフリーズドライにするやつ」ぐらいの理解でおり、先日DDS関連の明細書を読んでいた時にも何度も登場していたのですが、特に意識して(なぜ凍結乾燥にするのかなど)読んでいませんでした。
こちらも、原理、目的、他の乾燥方法との違い、明細書からみた用途などをまとめ、関連の明細書を5件ほど読みました。
読んだ明細書は、ポーラス構造にしたお菓子、乾燥菌体(乳酸菌)の生残率を高める方法などです。
ポーラス構造が得られる、熱に弱い対象物を乾燥させることができる、保存が容易になることなどが凍結乾燥方式の利点です。
食品などではよく、「スプレードライ方式」という乾燥方法も出てくるのですが、こちらは噴射した液体を加熱して乾燥させ固体にするものなので、やはり熱の影響を受けます。
ただ、凍結乾燥よりも効率良く製造はできるので乾燥させる対象物によっては、明細書上で「スプレードライ方式が好ましい」と明記されていました。
今なら、その一文を見たら「この組成物は熱の影響はそれほど関係ないのか」などと瞬時に頭に浮かびますが、昨日読んでいたら間違いなく読み飛ばしていました。
明細書を読む深さと速さは、やはり連関性を持った知識の量によるのだと思います(講座でいわれている通りですが)。
手が勝手に動くレベルでできるように、とにかく量をこなします。