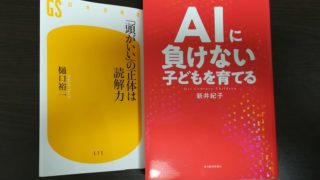学習内容
- 血管モデル対訳シリーズの残りを自力翻訳(3000wほど)+ビデオ視聴
- セミコンジャパン準備(バイオメディカル×ナノテクについて整理)
- ツールをいろいろ試す(Xbenchなど)
- 治験セミナーの課題文の参考訳例との差を見つめる
<イベント参加>
- JTF翻訳セミナー「製薬・治験翻訳の道しるべ」
- セミコンジャパン+女子会
引き続き、差を見つめる作業
先週から引き続き、血管モデルの対訳シリーズがメインでした。
先週までは1文訳してビデオを見ていましたが、今週は残り半分をまとめて訳し、判断に迷った箇所をメモしておいてからビデオを視聴することにしました。
今週の対訳学習の気づきは先週とほぼ同じで、「わかっている分野は違和感に気づきやすく、そうでない分野では迷う」ということでした。
具体的には、造影CTで血管を撮影する際の「a contrast medium is jetted」(造影剤をjetした)には、「注入だから本来ならinjectedじゃないのかな」と瞬時に反応できるのですが、
その一方で3Dプリンタのデータがない(オブジェクトがない)領域を示すspace domain(空間領域)は自信が持てずかなり調べて、「空間領域」とするしかないのかなぁという結論に達しました。
訳出してから少し間が空いてから自分の訳文とメモ書きを見つつ、ビデオとの差を見つめています。
今の所は「違和感フィルタ」はわりと精度よく機能しているなと自己評価していますが、訳文の質という点では難あり(相変わらず主語と述語が遠くて読みにくいなど)なので、終わったら一度整理します。
一流のプロとの差を見つめる
今週、JTF翻訳セミナー「製薬・治験翻訳の道しるべ」に参加しました。
今は特許翻訳の学習に軸足を戻していますが、これはどうしても参加したかったのです。
というのも、今回の講師はあのバイオ・メディカル翻訳者・メディカルライターの山名さんだったからです。
「あの」と言っても「どちらの?」となる方が大半だと思いますが、以前山名さんのブログが何かのタイミングで講座ビデオに登場した時に、私は実はかなり惚れ込んでしまいました。
その文体からにじみ出るマインドと仕事に対するプライドに、です。
(私が言うのもおこがましいのは重々承知の上です)
だから突如治験翻訳の勉強を開始した・・・というわけでは決してないのですが、影響を受けているのは確かです。
何よりも、ブログで「独学するための学習素材」を惜しみなく提供してくださっていて、それを一つ一つ確認して、「確かにこの方法で積み重ねていけばできるだろう」という確信が得られたからです。
私は「勉強量」が足りていなかったため、現時点ではこの分野では結果を出すことができず、方向転換してひとまずは特許翻訳で安定稼働を目指すことにしたのです。
今回のセミナーを聴講して、足りないものは勉強の絶対量だけではなかったことに気づきました。
私に足りないもの、それは「プロ意識」でした。
今回のセミナーは、事前課題が配布されていました。
任意ですが、提出すると当日匿名で「間違えやすいポイント」などとして取り上げてもらえる可能性があるとのことで、真剣に取り組んで提出しました。
自分のミスを取り上げて頂いて、「なるほど」と直接的に学びを得られたことも大変ありがたかったのですが、それよりも、同じ文章をこの道のトッププロがどういう思考を経て訳出するのかがわかったことが一番の収穫でした。
ここで具体的な例を挙げることはできませんが、例えば課題文のみでは読み取れない部分は引用文献をチェックして確認したり、ある言葉の医薬・治験分野で使用される意味と一般的な意味との射程の違いを明確にしたりして訳出されていました。
また、治験分野であれば特にエンドクライアントのスタイルガイドに合わせることが求められます。
その合わせ方、資料の探し方などは「わかっているつもり」でしたが、課題文訳出時に私はできていませんでした。
ああ、こういうひとつひとつのちょっとした「差」が積み重なって果てしないプロとアマの差になるのだな、ということがよくわかったのです。
帰宅後に、一文一文解きほぐして、差を見つめつつデータベース化していきました。
今回得たことは治験翻訳だけでなく、もちろん特許翻訳にも活かせることです。
何より「プロとの差」を直接感じたことで、(単純な憧れというわけではなく)こういうマインドとスキルを持った翻訳者でありたいと強く感じ、その後「一文一文に向き合う姿勢」が少し変わりました。
この分野に興味がある方は、山名さんのブログをご覧になることをおすすめします。
その他、治験翻訳入門も一通り目を通しておくと、概要がつかめます。
そしてイートモを販売・メンテナンスされている成田さんのブログも要チェックです。
イートモももちろん神ソフトなのですが、日々更新されているブログにものすごく学習のヒントが詰まっていますので読み飛ばしてしまうのはあまりにもったいないです。
メディカルライターになるには、という切り口ですが、治験まわりについて一通り(かなりざっくりですが)下記の記事にまとめてあるのでこちらもよろしければどうぞ。

セミコンジャパン&女子会
今週はセミコンジャパンにも参加しました。
去年は関西におり、まだ会社員でこの時期ちょうど仕事が忙しく参加を断念しました。
それを思うと、1時間ちょっとで行けてしまうというお手軽さ。
またかと思われそうですが、「引っ越してよかった!」です、ほんと。
セミコンジャパンの参加メモは次の記事にまとめました。

今回、100%満足だったかというと実はそうではなく、要改善ポイントが大きく分けて2点あります。
- 正味半日の参加でしたが、さすがに半日は短すぎた
- 最先端技術や注目の技術などについても情報収集すべきだった
もともと1日のみの参加予定でしたが、体調の関係で1日体力が持ちそうになかったので半日にしました。
会場をざっと回る+じっくり見たいブースをいくつか回るだけなら、半日でも十分です。
ですが、せっかくならばセミナーを聴講して最先端に触れたいですし、やはり最低1日、できれば1日半~2日は必要ではないかと思います。
今回は時間の関係もあり、知識を深めていきたいバイオメディカル分野への応用を中心に見ていきました。
ただ、セミコンの中心は前工程の製造プロセス関連であるので、そのあたりの最新情報を頭に入れた上でブースを回った方が、もっといろんなフックがかかって学びが多かったのではないか、と後で思いました。
そしてお待ちかねの講座受講生・卒業生の皆さんとの女子会です!
遠方からお越しの方もいらっしゃり、こうやって会えるのは本当に貴重な機会だなと思いました。
ツールの使い方や展示会情報など、今回も有意義な情報交換ができました。
女子会参加の皆さん、ありがとうございました!
来週の予定
今週から実質そうだったのですが、来週から完全学習モードに入ります。
計画からビハインドしている対訳シリーズを進め、終了次第岡野の科学+特許明細書メインに移行します。
今朝のブログに書いた通り、読解力を鍛えるには要約がよいそうです。
明細書というちょうどいい題材があるので、読んだ明細書の要約は都度twitterででも配信する予定です。
読解力も上がって勉強にもなって一石二鳥。
これで読解力がメキメキ上がったら、kindle本でも出せそうですね。
「2桁のかけ算で落ちこぼれたアラフォー女が読解力を超向上させて一流の翻訳者になった話(仮)」あたりで。