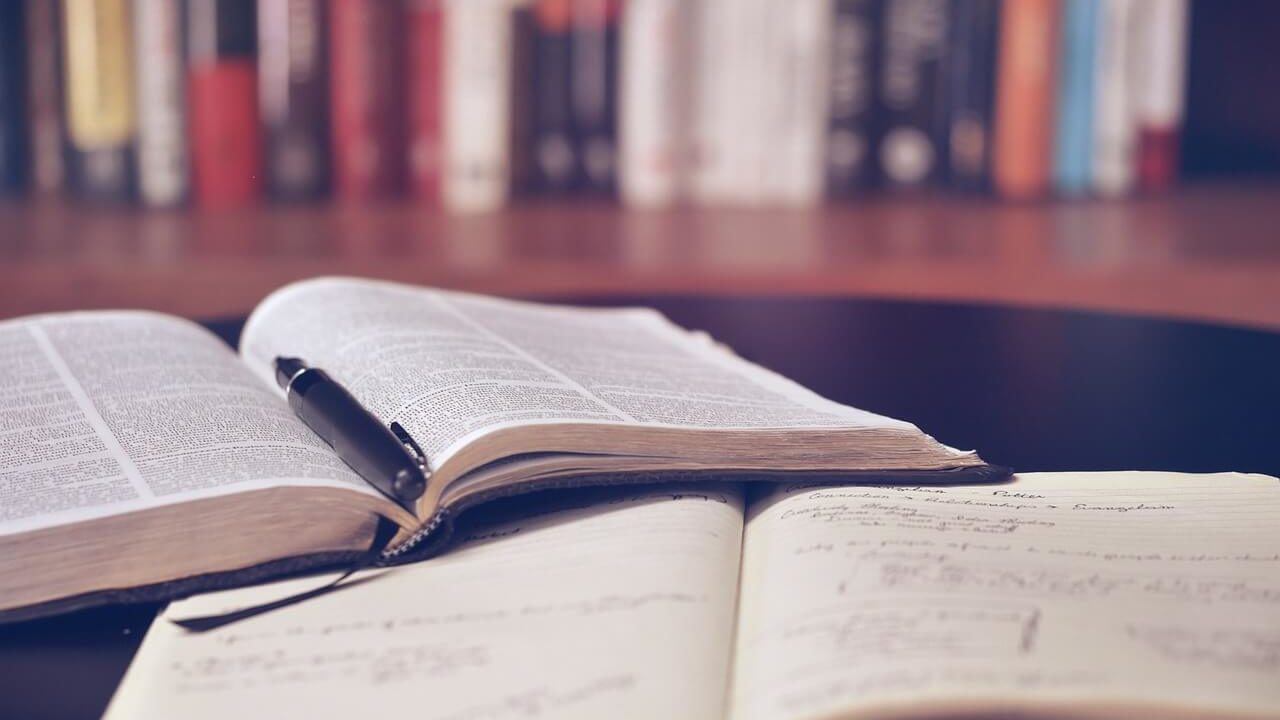先週からはまっていた表面張力なんですが、ようやく出発地点に戻ってきました。
IBM社レジストの対訳シリーズの学習で、(これも実質全然進んでないのですが)スピンコート後のレジスト上の溶剤を除去する工程について調べていた時に、「表面張力」という言葉が出てきたことがきっかけでした。
レジスト関連だけでも、表面張力に起因する製品不良や、逆に表面張力を利用した加工方法など、本当にこの現象は幅広く使われているんだなということがわかりました。
今回、下記のようにぐるっと一回りしてきたんですが、これはまだ、表面張力ワールドのほんのほんの一部だろうなあと思います。
表面張力って何だっけ?(表面自由エネルギー、接触角など)
↓
界面活性剤の役割(表面張力を下げる原理、泡、ミセル、吸着の原理など)
↓
表面張力差がもたらすもの(対流、コーティング・膜形成不良など)
↓
レジストと表面張力(疎水化表面処理、マランゴニ洗浄、超臨界乾燥など)
今までよりも「じっくり」を意識して、なんとなくわかるけど説明できない言葉が出てきたら、一度立ち止まって調べてある程度納得して進むようにしました。
調べているうちにあれもこれも気になってしまい、脇道からさらに分岐した道に入りそうになることもしばしばですが、「こっから先はけもの道だ」と思って立ち止まれるようになってきたかな、と思います。
とは言え、あたりをつけて(仮説を立てて)検索するということができていないのと、その言葉の持つ世界が見えていなくて検索キーワードを絞り込めないことで、余計な時間がかかっている感じはあります。
まだ点と点をさんざん迷いながら、大回りになりながら、鉛筆でぐぐぐっとつないでいるような状態かなと思います。
用例.jpで表面張力で検索し出てきた結果をざっと眺めていたら、お、結構わかるじゃん、という感覚が得られたので(今日は感覚ばかりですね・・・)、こんな感じでやっていけば、少しずつ線に電流が流れて、どこかでスパークするのかなと思います。
最後に、先週の記事(スピンコートと表面張力)で、wikipediaの表面張力の項の一文、
「温度が上がることで分子間の運動が活発になり、分子間の斥力となる」の「分子間の斥力」がなぜ起こるんだろうか、ということを書きました。
これはただ、分子間の運動が活発になることでお互いにぶつかり合うことが多くなるから斥力となる、ということを言っているだけだと思うのですが。これが違っていたら、もう1周回ってこい、てなりますね・・・
7/29(日)の学習記録
学習時間:13h
*買い物+美容院で2時間ほど外出
項目: スピンコートと表面張力の明細書の続き+まとめ
目標: 2h 実績: 12h
項目: Tradosを操作してみる
目標: 1h30m 実績: 1h
7/30(月)の学習記録
項目: レジスト関連の表面張力について調べる
目標: 6h50m 実績: 6h50m
7/31(火)の学習計画
項目: ノート整理+IBM社レジスト特許を読む(1)~
目標: 7h